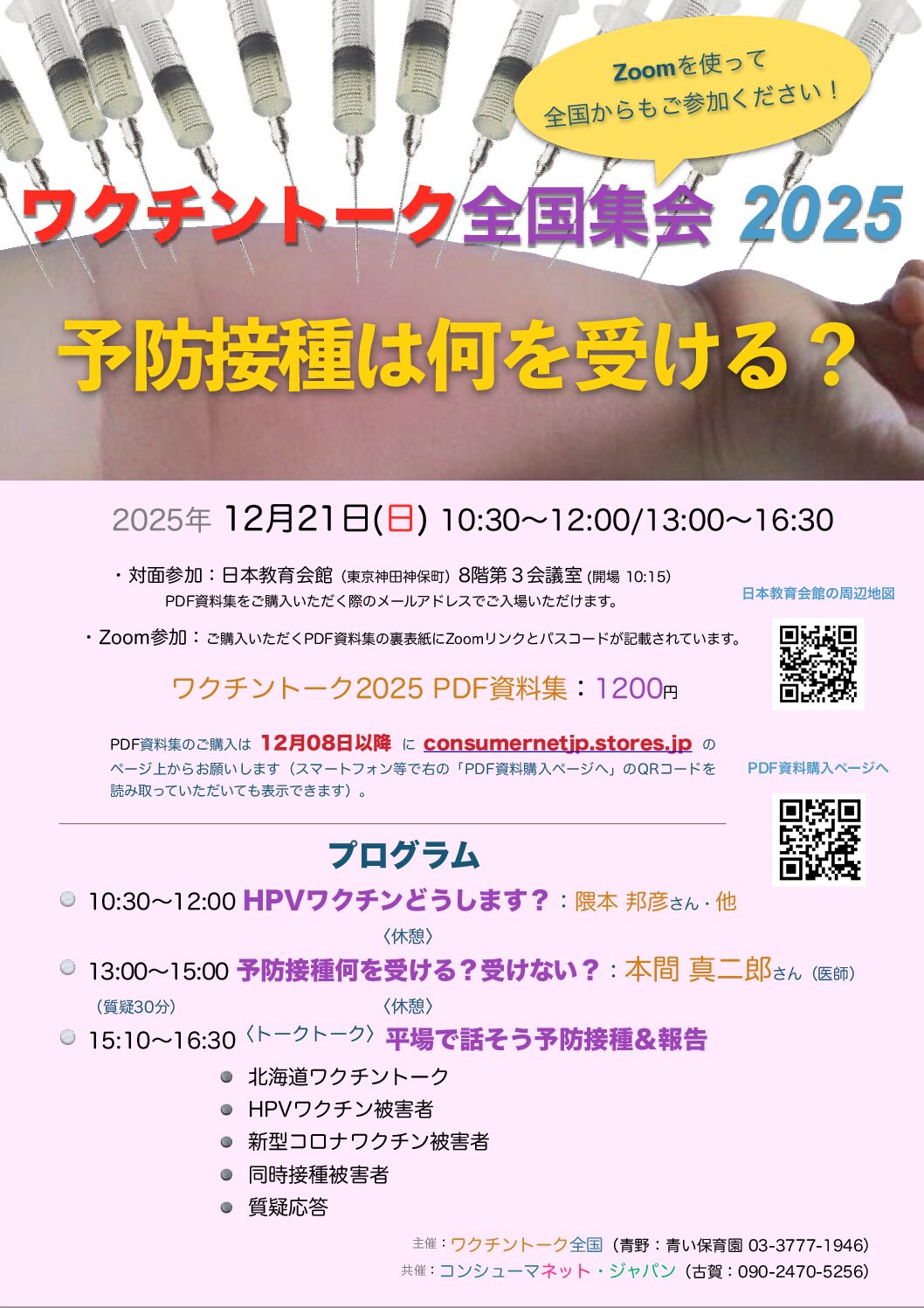赤ちゃんの同時接種 即時見直しを!その3 アーカイブ 同時接種死亡例 2 ヒブ・肺炎球菌ワクチン同時接種で死亡の女児 審査請求を経て2024年1月26日提訴
2011年3月にヒブ肺炎球菌の同時接種後の突然死報告があり、一時接種見合わせとなりました。1週間で3人、1ヶ月で6人の接種の死亡が明らかになったためです。その後わずか1ヶ月後に再開されました。再開の理由を厚労省は、「専門家の評価によると、現在得られている知見の範囲では、これらのワクチンの安全性について、心配はない」とされています。
○ 接種と一連の死亡との間に、現時点では直接的な明確な因果関係は認められない。
○ 接種後の死亡事例で、接種との因果関係が分からないものは、海外でもある程度報告されている。
○ これまでの国内外の調査では、小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンあるいはこれらとDPT(3種混合)ワクチンなどの複数のワクチンを同時に接種しても、重い副反応の増加は報告されていない。」としていました。乳児突然死症候群と同時接種の関係が取り沙汰され、関連する研究班も立ち上げられましたが、結果の報告がされないまま現在に至っています。(2025年4月時点で裁判過程で被告国側からの資料として報告書が提出されました。後掲:これについては別途検証します:うつ伏せ寝や母親の喫煙などを因子とする評価に値しない報告です)
ヒブ肺炎球菌ワクチンは必要か?病気の実際は?
2001年の薬のチェックは命のチエックの対談による発言では、日本でのヘモフィルス・インフルエンザ菌のタイプb(Hib ヒブ)による侵襲性感染症は予防接種導入前のデータでは、年間700人、うち髄膜炎の発生が400人と推定されていました。死亡率は0.4〜4%、多く見積もって18人。聴力障害などを含む後遺症が多いときで27.9%(110人)との発言がありました。
感染症情報センターの報告によると、侵襲性インフルエンザ菌感染症(IHD)は、2013年4月から感染症法に基づく五類感染症全数届出の対象疾患となったためその後の流行状況は正確に把握されています。報告数は経年的に増加傾向を示し、IHD症例の届出時点での死亡の頻度(ここでは致命率とする)は、2013年から2018年までは5.6~8.3%でした。ワクチンが定期接種化したのに死亡率は増えていると思われます。
2008年12月、乾燥ヘモフィルスb型(Hib)ワクチン(破傷風トキソイド結合体)による任意接種が開始され、2010年11月には「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」の開始とともに、5歳未満の小児に対するHibワクチン接種は全国的に公費助成対象となりました。さらに、2013年4月の予防接種法の改正に伴いHibワクチンは定期接種に組み込まれました。通常のHibワクチン接種スケジュールにおいては、生後2~7カ月未満の乳児に対して接種を開始し、3回の初回免疫後おおむね1年後の追加免疫が推奨されています。
2006~2010年には、年間 347~477例の細菌性髄膜炎の報告のうち、56~83例がヘモフィルス・インフルエンザ菌に起因していました(。2006~2012年のヘモフィルス・インフルエンザ菌による髄膜炎患者の93%(400例中 372例)は、5歳未満の小児でした。また、Hibワクチン公費助成開始後の2011年には49例と減少傾向を示し、2012年には14例まで減少しました。この2011~2012年のヘモフィルス・インフルエンザ菌による髄膜炎患者の減少は、2歳未満の小児で顕著だったとされています(図1)。
厚生労働省研究班事業として2007年から始まった「ワクチンの有用性向上のためのエビデンスおよび方策に関する研究」(庵原・神谷班)によって10道県における5歳未満人口10万人当たりのHibによる侵襲性感染症の平均罹患率が調査されました。Hibワクチン公費助成前の2008~2010年には髄膜炎 7.7、菌血症を伴う非髄膜炎 5.1でしたが、2012年には髄膜炎 0.6(減少率92%)、菌血症を伴う非髄膜炎 0.9(減少率82%)にまで減少したことが明らかになっているとされています(本号10&11ページ)。同様の傾向は、全国の厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)の検査結果の集計からも示唆されました(本号13ページ)。
海外ではHib ワクチン導入後に非b型(NTHiを含む)による侵襲性感染症の増加が報告されている。国内においては、最近になって、Hibワクチン3回接種後のf型による髄膜炎例が確認されており(本号11ページ)、またNTHiによる小児や成人の侵襲性感染症が報告されている(本号4&5ページ)。このような背景から、小児に対するHibワクチンの定期接種後の小児および成人におけるHibのみならず、b型以外の莢膜株およびNTHiによる侵襲性感染症の動向の監視が必要である。2013年度から、感染症流行予測調査事業の感染源調査として、本菌の莢膜型解析を含めた病原体サーベイランスの実施が予定されている。(以上感染症情報センターHPより)
2010年の事業接種以後、近年は報告はされず定期接種として定着したかに見えますが、b型以外の型の出現があります。
同時接種後死亡については、複数接種によるワクチンとの因果関係が不明とされたまま否認されていることが明らかになっています。
肺炎球菌による侵襲性感染症と副反応
一方、肺炎球菌による侵襲性感染症は罹患者が1200人から1300人。内訳は髄膜炎が役150人、死亡は2%で3人くらい、後遺症が10%で15人くらいと言われています。
7価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV7 プレベナー)は2009年10月に承認され、2010年11月に小児に対するPCV7の公費助成が開始されました。その後、2013年4月からPCV7は5歳未満の小児を対象に定期接種化(A類)され、さらに2013年11月からはPCV7は13価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV13)に切り替わりました。一方、2014年10月からは65歳以上と、60歳以上65歳未満の者で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生労働省令で定める者の高齢者に対する23価肺炎球菌ワクチン(PPSV23)の定期接種化がされました。さらに、2014年6月にPCV13の65歳以上の成人に対する適応が追加されました。小児・成人における肺炎球菌ワクチンの効果を監視する目的で、2013年4月、侵襲性肺炎球菌感染(invasive pneumococcal disease: IPD)が感染症法に基づく感染症発生動向調査において5類感染症全数把握疾患(以下、5類全数把握疾患)となりました。また、2013年度から厚生労働省指定研究班「成人の重症肺炎サーベイランス構築に関する研究」(成人IPD研究班:研究代表者:大石和徳)が発足し1)、10道県における成人IPD患者の原因菌の血清型分布の調査を開始しました。それによると、5歳未満の小児と60歳以上の高齢者に症例の集積があり、男性が57.9%を占めた。IPDの罹患率(人/10万人・年)は5歳未満が6.13、65歳以上では2.43であり、高齢者の罹患率は5歳未満の小児より低かった。一方、致命率では5歳未満が0.31%と低いのに対し、65歳以上では10.39%と高かった。5歳未満では、菌血症(67.6%)が最多で、菌血症を伴う肺炎、髄膜炎がそれに続いた。一方、65歳以上では、菌血症を伴う肺炎が47.2%を占め、菌血症は34.8%、髄膜炎は17.8%であった。とされています。
5歳未満のIPDの臨床像は菌血症が大半を占めていた。今回の成人IPD症例の臨床像では菌血症を伴う肺炎が約5割を占めた。また、髄膜炎の症例数は小児より成人において多く認められたとされています。非PCV7血清型によるIPDの増加に対応して、2013(平成25)年11月からはPCV7に代わってPCV13が小児用定期接種ワクチンとして導入され、今後は血清型19AによるIPDは減少すると予想される。
同時接種後死亡例
一方で毎年同時接種死亡報告があります。
ワクチントーク全国事務局長の青野典子さんの2024年2月4日のタネまき会での報告によれば
Hib・PCVワクチンを含む同時接種後の死亡報告 84件
•Hib・PCVワクチンの単独接種後の死亡報告 10件
•その他のワクチンの同時接種後の死亡報告 9件
•その他のワクチンの単独接種後の死亡報告 33件
(インフルエンザ・高齢者肺炎球菌ワクチンを除く 副反応疑い検討部会より 青野さん作成)
審査請求から提訴まで
Bさんは、2019年6月5日に処分行政庁Sに対して予防接種法15条1項に基づく死亡一時金等の請求文書を提出しました。Sは東京都を経由して国に認定審査部会にて審議され、否認の通知が2020年3月17日付通知がされました。Bさんは、令和2年6月15日、東京都知事に対し、本件処分の取消しを求める旨の審査請求を行いました。
審査請求において、原告は、1 死因の特定が明確でないこと、2 接種直近の月におけるKセンターの検査の不備・H小児科医院等における接種時期判断における過失の可能性、3 本件予防接種による死亡における接種と死 亡の因果関係を認定する場合において重要な死亡までの日数を誤ったまま判断したことによる誤り等を医師の意見書等を添付して指摘し、Bの死亡と本件予防接種の因果関係に関する判断の誤りを主張。
さらに令和2年9月1日、Sの弁明書に対する反論及び意見書を提出して、本件処分が取消されるべきものであることを主張しました。
令和3年3月17日には、Bと古賀に口頭意見陳述の機会が与えられましたが、Bの主張は受け入れられず、令和5年7月27日、知事は、同審査請求を棄却する裁決をしました。
2024年1月26日、Bさんは審査請求で認定されなかったことから提訴に踏み切りました。今後の裁判の状況については追ってご報告します。
(参考)
審査請求についての意見書
2020年3月17日 特定非営利活動法人コンシューマネット・ジャパン理事長 古賀 真子
- 出生から死亡まで
2017年9月29日生まれ。出生時体重3580g、健常。
2019年1月20日(1歳3か月時)姉から家族全員がインフルエンザA型に罹患。
1月23日、けいれん発症(*インフルエンザ感染かは不明)→肺炎の傾向の診断。けいれんが続く。
1月24日インフルエンザによる熱性けいれんとの診断。30分前後のけいれん重責。神経学的な後遺症はないとされ、エコー調査は母親が要望したがなされなかった。脳症の可能性と診断。ICUへ。高熱続く。抗痙攣剤・解熱剤の投与続く。複雑型熱性痙攣。
1月28日解熱して48時間たって痙攣がでなかったため退院。あらためて「インフルエンザAによる複雑性熱性けいれん」との診断。
1月28日退院、帰宅10時間後に発熱。翌日1月29日の夜に発熱認め、解熱剤を投与し、解熱する。1月末~2月初旬は快調の傾向。2月にハイチェアから転落してH小児科医院を受診。特に問題なしとして経過観察となる。
3月1日、Hibワクチンと、肺炎球菌ワクチンの4回目を接種。(1歳5ヶ月)
3月5日、いつも通り起床するが昼頃より元気がなくなった。けいれんの前兆と思われた。13時10分に入眠。13時半ごろから大人用ベッド午睡。16時9分に通常起きる時間に起きてこないために確認に行くとぐったりして息をしていなかった。16時16分救急要請し16時22分に救急到着。呼吸、脈拍なく、16時41分に K医療研究センターに初療。心電図停止のまま。18時12分死亡確認。死因特定できず、観察医務院で行政解剖。直接死因は急性肺水腫、部検初見では急死。便からノロウイルス検出(下痢はなし)。
- 疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査会分科会(認定部会)の議論と疑問点
接種後5日目に肺水腫が起きるかについては死後の状態を診た時に見られる状態なので死因とは言えない。乳児突然死症候群であるためには他の原因がない場合でありこの件はあたらない。認定部会では病名は突然死で認定は4とされた。4とされた決め手は、「もともと熱性痙攣の群発を起こす子どもで、ワクチン接種で通常熱が出るのは0から2、3日以内、5日目に少し痙攣様の症状もあるようなエピソードもあり、その後亡くなられているのですね。何が起こったかちょっとよく分からないので4なのか、微妙な日数のところで3bなのか、私の印象としては4に近いのです」
発症日数について誤解がある上、原因特定に至らないのに無理やり肺水腫という死後の病名からワクチンが原因との因果関係を強引に否定している。本件は黒部意見書にもあるように、インフルエンザA感染症でかつ痙攣重積を繰り返し、解熱剤の使用によりライ症候群を起こし、それで肺水腫を生じていて、それが解剖時に判ったと考えるべき。
(議事録参照)
- 黒部信一意見書
意見書(下線は筆者)(審査請求追加提出)
1 本件は、判定では「2019年1月にインフルエンザAに罹患した際、複雑型熱性痙攣で入院加療されております」。「30分前後の痙攣重積発作が2 回ありましたが、神経学的な後遺症などはなくエコーのフォローアップもありませんでした。」という既往があるという前提をもとにして、2019年3月1日に実施された Hibワクチンと肺炎球菌ワクチンを用いた定期の予防接種と、突然死との因果関係について検討されました。
2 事実経過は、2019年3月5日 ( ワクチン接種後4日後 ) の16時12分頃心肺停止状態で発見され、18時12分に死亡が確認されました。行政解剖が行われ、死亡の直接の原因は急性肺水腫と診断されました。そして「当該予防接種によって肺水腫を発症することは考えにくいこと等から、当該予防接種が突然死を引き起こしたと考えるのは困難です。」とされました。つまり救済否認の理由として、死亡の直接の原因はあくまで「急性肺水腫」であり、「当該予防接種によって肺水腫を発症することは考えにくいこと」、さらに「また一般に、小児の突然死例は一定程度存在すること等から」ということが根拠になって「当該予防接種が突然死を引き起こしたと考えるのは困難」としています。
3 まず前提となる複雑型熱性痙攣とされたことと、痙攣発作の治療について検討します。 患児は、2019年1月23日に初めての熱性痙攣を起こし、15分前後で痙攣は止まったように見え、武井医院へ行き、そこでまだ細かい痙攣が続いているとして成育医療センターへタクシーで行きました。成育医療センターに到着した時には意識も回復し、徒歩で入り、発語もありましたから痙攣はおさまっています。
初めての熱性けいれんの場合には、母親の気が動転して患児を抱きしめたりしていると痙攣が長引くこともよくあることで、そっと寝かせておくことが大切です。それで初回の発作であり、かつ来院時点では意識も回復し、徒歩来院している子を「痙攣重積状態」と診断して入院させ、有効性のエビデンスの無いホストインの静注と、痙攣発作を誘発しやすい解熱剤を繰り返して連続使用しています。
初めての熱性痙攣では一般的にも、日本のガイドラインやネルソンの小児科学書でも通常使われるエビデンスの確立されているジアゼパムを使用せずに、てんかんの痙攣発作の薬であり、熱性痙攣にはエビデンスの無いホストインを予防的に静脈注射しています。その後に起きた痙攣発作にもホストインを使用したが効果はなく、痙攣重積発作が3回起きています。そしてミダゾラムの静注でようやくおさまりました。 最初からジアゼパムかミダゾラムを使用していれば、繰り返しての痙攣発作を止められたかもしれません。
脳波もとらず、再度の血液検査もせずに退院させてしまったことは、あくまで単純型熱性痙攣としか見ていなかったのだと思われます。この時の痙攣重積の原因が、本当に熱性痙攣の複雑型であったのかという証明がなく、他の疾患の否定、除外診断がなされていません。
4 解熱剤の連続使用について検討します。 通常熱性痙攣の場合には、解熱剤は母親の不安をやわらげる目的でしか使わないのが普通ですから、入院した場合には必要のないはずです。それなのに解熱剤を連続して使用しています。 熱の上がり下がりの時に痙攣発作の起きることは、熱性痙攣では良く知られたことです。それなのに連続して解熱剤を使用し、その為に熱が上下したために、繰り返して痙攣発作を起こすことになった疑いが残ります。熱性痙攣の痙攣を止めるには、解熱剤ではなくジアゼパムを使 います。
5 インフルエンザへの解熱剤の使用とライ症候群について検討します。インフルエンザ感染症にアスピリンを使うことによりライ症候群が生じることは良く知られたことだと思いますが、アセトアミノフェンによってもまれではありますが、ライ症候群が起きることは世界的に報告されています。それゆえ軽症のライ症候群になった疑いも否定すること はできません。ライ症候群の軽症、特にI度であれば、自然回復することもあると言われています。これを否定する根拠なく退院させてしまったのです。
6 肺水腫の診断について検討します。本件は、明らかに肺水腫を起こしており、その原因または病態を不明とするべきではなく、肺水腫を起こした原因を遡求すべきです。本件の認定を審議した第135回疾病・障害認定審査 会感染症・予防接種審査分科会の議論でも、「肺水腫は様々な原因でこういった状態 ( 肺水腫 ) がよく見られる」とされ、また「肺水腫が突然死の原因とは考えられない」という意見がありました。肺水腫が原因とは考えにくいが、それしかないから「肺水腫が死因とした」と判断したとしか思えません。
肺水腫が死因では不自然です。死因とはなり得ません。
ネルソンの小児科学書によれば、肺水腫は「複数の異なった病態の結果生じる問題であり、小 児急性疾患によくみられる」とあります。その多数の肺水腫の病因の中で、本児の場合を検討してみました。それで解剖所見から判断すると、「混合原因、原因不明」の中の「神経原性肺水腫」の可能性が残ります。
それは1か月前の痙攣発作を繰り返したことに起因する可能性です。残念ながら、脳波をとっていないことにより、決め手に欠けますが、何らかの「大脳損傷に続いて生じる交感神経系の大量放電は、肺および全身の血管収縮を促進し、血液は肺血管へ移動するために毛細血管圧が上昇し、肺水腫が生じる」とネルソン書にあるのに該当することを否定することはできません。
脳波をとり、異常のないのを確認して退院させるべきでした。これによる肺水腫が隠れていて、予防接種による死亡により判明した可能性を否定することは できません。つまり、インフルエンザA感染症でかつ痙攣重積を繰り返し、解熱剤の使用によりライ症候群を起こし、それで肺水腫を生じていて、それが解剖時に判ったと考える方が妥当と思います。脳波をとらず、血液検査による肝機能やアンモニアの検査を退院前にはしていません。ですから否定も肯定もする根拠はありません。
7 剖検では、脳浮腫は明らかではありませんでした。ただし、死後の頭部CT所見では私の経験から何となくおかしく感じ、軽い脳浮腫も疑われる所見で、僅かに脳室が小さいかと思われます。もっとはっきり写っても良いと思います。必要なら小児放射線診断専門医の鑑定を受けても良いかと思います。あくまで軽いライ症候群であれば、ごく軽い脳浮腫となるので、死後には消えてしまってもおかしくはないです。私は初期の頭部CTの導入の頃に関わり、当時は撮影もしました。その頃にはまだ新生児のビタミンK内服はなく、新生児のビタミンK欠乏による生後一か月の頭蓋内出血の患児を自分で頭部CTを撮影診断し、治療したことがあります。明らかな頭蓋内出血で、ビタミンKの静注により出血は止まり、その後放射線診断については 頭蓋内の出血巣も消失したことを経験しています。その後小児放射線診断専門医の指導も受けました。乳児の病理解剖にもたびたび立ち会ったことがあり、脳浮腫の軽度の場合には肉眼的には判断が難しいと思います。肝臓所見も同様です。小滴性脂肪肝は明らかではありませんでしたが、通常は剖検でしか脂肪肝を見ていません。軽度のライ症候群でしかもワクチンさえしなかったら生存して正常に復帰したかも知れない程度の本例であれば、この時点で小滴性脂肪肝がなくても否定することはできないと思います。
3月5日の死亡後の剖検時の血液検査では肝機能AST(GOT)は514と716、ALT(G PT)が168と276、LDHが1997と879、しかもアンモニアが500以上でした。これはライ症候群に見られる状態ではないでしょうか。この時になって判ったことであって、 その間には検査していませんので不明ですが、既に退院時から軽度あったことが疑われます。死亡後の検査データですが心肺停止判明後2時間程度なので、数字的には多少変化していると 思いますが、異常データがあったことは間違いないと思います。軽いライ症候群の場合には、 特に明らかな神経学的な異常がないような軽度の場合には、軽い脳圧亢進も慢性硬膜下血種の ように軽度であり、自覚症状も少なく、表面化しないし、剖検でも判断は困難と思います。幹細胞も軽度のものは完全に正常化すると言われており、小滴性脂肪がその時に解消されていたと考えてもおかしくはありません。
8 接種後の日数についてまた審議会では「熱性痙攣の群発を起こすようなお子さんで、ワクチン接種して・・5日目に 少し痙攣様の症状もあるようなエピソードもあり、その後、亡くなられているのですね。」「微妙な日数のところで」とあります。5日目とされ微妙と言われますが、正確には 4 日目と思います。4 日目ならさらに近づくのではないでしょうか。
3月5日の「13時半頃寝た時、左目が半目、首がびくびくしていたようにみえた」というのは、 けいれん発作と言っても良いと思います。13時半頃は意識もなく、そのような状態であったのです。これを予防接種が誘因で起きたことではないとどうして否定できるのでしょうか。
9 予防接種健康被害救済制度は、むしろ医師がおかしやすい予防接種事故や一般に見逃しやすい 小児の健康状態の把握の過誤による予防接種事故の救済にあると思います。それを医学的に明 らかに否定できる根拠もなく救済をしないということは、予防接種を推進するという国の方針にも反して、多くの市民に対して予防接種事故の不安や予防接種の忌避を助長することになる のではないでしょうか。それを防ぐためにも、否定できない以上は救済すべきと考えます。
この件でも、あくまで予防接種の接種後4日目という時に起きた死亡が、全く予防接種と関係がなく、明らかに別の原因で起きたという証明がない限りは、この制度で救済すべきだと考えます。
医療においては、厳密な因果関係を求めることは難しく、かなりの程度の蓋然性が認められることで充分だと思います。その意味でも、より水準の高い医療が日本の地に根付くことが求められています。
元東大医学部長の白木博次先生が提唱し、過去の予防接種過誤事件訴訟で確定されたものとして、「医療の事故または過誤の因果関係における条件としての、四原則」があります。それは、
1)医療事故または過誤とその症状とが、時間的、空間的に密接していること。 2)他に原因となるべきものが考えられないこと。 3)事故または薬剤の作用とそれによって生じる結果が、原則として、質量的に強烈であること。 4)事故発生のメカニズムが、臨床的な観点から見て、科学的、学問的に実証性や妥当性があること。
以上を充たすものを、因果関係があると判断されます。」この事件でも、この論理は適用されると考えます。
10 痙攣の定義として「一点凝視や動作停止のみで痙攣をともなわない意識障害であることもある」といいます。3月5日13時半頃の状態はそのような状態であったのです。これは何らかの大脳の障害があって、大量放電で痙攣発作が起きたことが疑われます。だから、1月に痙攣重積状態を起こして入院した時に脳波検査をすべきでした。3月5日のこの症状が、剖検時の血液検査のデータと共に、インフルエンザに対する解熱剤アセトアミノフェンの使用により、軽症のライ症候群を起こしていた疑いが持たれる根拠です。
11 単純な熱性痙攣では予防接種禁忌にはなりませんが、複雑型の場合には、明らかに予防接種を受けられるだけの安定して健康な状態が確認できていなければなりません。複雑型熱性痙攣なのに脳波確認をしないままに、また退院時の検査をしないままに予防接種したことに問題があると思います。その確認を経ずして接種したことは、予防接種が、けいれん発作の引き金になっ たことを否定することはできないと思います。
けいれん発作が30分以上続いたり、一回の発熱の病気で繰り返しけいれん発作を起こすのは 複雑型熱性痙攣になりますが、初回の発作を止める治療の失敗もあるのではないかと思います。
12 国立成育医療センターの各科は日本の小児医療の最先端を切り開いていました。解熱剤を使用することは、明らかに免疫を抑制することであり、水痘とインフルエンザへの使用でライ症候群が起きることから、先進国では解熱剤を使用しなくなり、クーリングや微温湯浴をしましたが、今はそれもしなくなりました。アセトアミノフェンによるライ症候群の報告もまれに見られています。いずれにせよ、詳細に検討すれば、一か月弱前のけいれん発作の原因診断がはっきりしておら ず、退院させてしまったことと不要な解熱剤の過剰な使用によることで軽症のライ症候群を発 症させてしまっていたことにあり、開業小児科医がいくら見た目で判断しようとしてもできる ことではなく、国立成育医療センターを信頼していたためにワクチン接種をしても良いと判断 したのではないかと思います。
以上、予防接種の接種前の状態把握、特に既往症の前提が正しく把握されていなかったことが明らかであり、そのような状態での判断では正しく判断することができなかったと思います。予防接種が引き金になって、軽度のライ症候群が存在し、予防接種をしなければ完全に回復することができたと思われる患児を死に至らしめたと言う疑いが残ります。
予防接種健康被害救済制度は、そのような予防接種事故をも救済する制度ではないでしょうか。現状では、「明らかに原因が別にあると診断でき、予防接種が原因ではない」という証明がない限り、否定することはできないと思います。
本件について、以上の疑いを医学的に否定する根拠がない以上、予防接種健康被害救済制度で救済すべきと思います。
令和 2 年9月 1 日 すずしろ診療所所長・小児科 黒部 信一
4反論書と処分庁の対応について
令和2年8月17日に処分庁S区より送付された弁明書は、本件請求を受け、令和元年7月25日にS区予防接種健康被害調査委員会で審議し、そこでは因果関係不明であるとの報告がなされ、令和元年9月30日に厚労大臣宛に東京都を通じて国の認定審査を送った(調査委員会議事録参照)。令和2年2月3日に国からの審査結果が東京都知事を通じて処分庁に通知された。同3月17日に請求人に通知を送付したこと、が記されている。令和2年6月15日に審査請求がされたことから事実の認否として(4)審査請求の趣旨及び理由は争うとしながら、反論は法の説明と請求の手順を書いているだけであり何の説明も検討もない。「本件処分は関係法令に基づき適切に行われたものである」とし、「厚生労働大臣が認定を否認した場合には、法に基づく給付を行うじことはできないことになる。そうすると、本件の場合、厚生労働大臣は処分庁に対し、本件請求について、「認定できません」との審査結果を通知しているため、処分庁は請求人に対して医療費・医療手当の支給ができないことになる」としている。これは本件の認定の可否について当事者能力を全く欠如した処分庁に対して反論書を提出させても意味がないことを示しており、被害者救済のための制度としてはいたずらに請求者を徒労に終わらせることになる。
請求者は令和2年9月1日に弁明書に対して反論と意見提出を行っている。
5ヒブと肺炎球菌ワクチン同時接種後死亡評価の問題点
- 救済の困難性 〜当初よりヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの同時接種後死亡等の原因は解明されていない
ヒブ(ヘモフィルス・インフルエンザ菌b型:Hib 以下、ヒブという)ワクチンは乳児期の細菌性髄膜炎を発症させる割合が高いとして、小児用肺炎球菌(プレベナー13;2013年11月から従来の7価ワクチン(PCV7 :7種類の肺炎球菌)が13価ワクチン(PCV13:13種類の肺炎球菌)に切り替え、以下肺炎球菌という)ワクチンと同時に導入されました。両ワクチンは、2011年から公費助成が始まり、2013年度から定期接種となった。
2011年3月には同時接種後死亡が報道された。同年3月2日から本日までに4例の接種後死亡が報告され(接種翌日死亡が3例、3日後死亡が1例)いったん中止が発表された。2歳の男子は室中隔欠損症、慢性 肺疾患、気管支喘息、てんかん、他の持病があったが、1歳未満の女子は右胸心単心室肺動脈閉鎖があったが他の2名には基礎疾患はなかった。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000013zvg.html
3月7日にはチアノーゼ、右心室 肥大等の基礎疾患がある6ヶ月未満の男子がBCGとヒブの同時接種でなくなった。厚労省は3月8日に開催した、医薬品等安全対策部会安全対策調査会及び子宮頸がん等ワクチン予防接種後副反応検討会の合同会合でにおける標記のとりまとめについて、ワクチンとの直接的な因果関係を否定する報道を流した。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000146lh-img/2r985200000146my.pdf
3月10日にはヒブワクチン(販売名:アクトヒブ)と三種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風・百日咳)とを同時接種した事例において、接種7日後に死亡したとされる症例の報告があった。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ac1.html
3月11日にはサノフィパスツール株式会社 第一三共株式会社がヒブワクチンの自主回収を行った。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014f5h-img/2r98520000014f6y.pdf
3月24日には事実上の安全宣言をするための資料が公開された。直接的、明確は因果関係はないとした報告書でした。
1 小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンのいずれにおいても、米国での 使用成績に関する論文や企業が収集した副反応報告からみて、接種後に一定頻度の死亡例が報告されている。
2 海外での死亡例の報告頻度は、小児用肺炎球菌ワクチンでは概ね対10 万接種で0.1~1程度、ヒブワクチンでは概ね対10万接種で0.0 2~1程度である。
3 諸外国の死亡報告の死因では、感染症や乳幼児突然死症候群が原因の大半を占めており、いずれもワクチンとの因果関係は明確ではない。国内で今回見られている死亡報告の頻度(両ワクチンとも対10万接種当たり0.1~0.2程度)及びその内容からみて、諸外国で報告されてい る状況と大きな違いは見られず、国内でのワクチン接種の安全性に特段の問題があるとは考えにくい。
(参考)国内においては、平成23年以降、接種者数の増加傾向が見られている。https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000167mx-img/2r985200000167oe.pdf
症例一覧表
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000167mx-img/2r985200000168db.pdf
その後、異例の速さで、3月28日には、「小児用肺炎球菌ワクチンとヒブワクチンを含む同時接種後の死亡報告を受けての接種の一時的見合わせについて、3月24日(木)にとりまとめられた薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会及び子宮頸がん等ワクチン予防接種後副反応検討会「小児用肺炎球菌ワクチン、ヒブワクチンの安全性の評価結果について」を踏まえ、4月1日から接種を再開することといたしました。」
同時接種についても詳細な検証はされなかった。同時接種は医師の裁量で必要な場合に許されることになっているが、接種される子どもや親の負担軽減を理由に同時接種が恒常化し、原則と例外が逆になっている。(詳しくは 受ける?受けない予防接種P48〜55)その後の副反応検討部会の報告でも同様の事例が毎年起きているが、当初の「安全宣言」に問題があったといえる。(2) ヒブと肺炎球菌 副反応の認定状況
2014年以降のヒブ肺炎球菌の副反応認定の結果である。2013年に定期接種化して以降、毎年死亡例を含む副反応報告が出ている。報告では毎年10名前後の死亡例が出ていますが、認定はまた別個の手続きが必要なので審議対象になった数は決して多くはないと思われる。まして審査請求もどれくらい出ているか不明である。申請しないか途中で断念することが多いと疑われる。副反応にあっても市町村窓口への届出から国の疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会(以下、認定部会という)での議論を経て認否がされるが、全体的な被害状況の氷山の一角であるとしか思えない。
<表まとめ ワクチントーク青野典子>
申請 61件(認定38 否認23)(否認については疾病名・障害名不明) 同時接種 52件(認定33 否認19)(認定のうち1件は障害児養育年金は否定されている) 単独接種 9件(認定 5 否認4 )※ 死亡で申請 9件(認定2 否認7) 障害児養育年金で申請 9件(認定3 否認6)(認定のうち2:認定者数一覧では2017年末には記載あり、2018年末~削除されている)
※任意接種ワクチンとの同時接種を含む(おたふくかぜワクチンなど任意接種ワクチンと同時接種の場合、厚労省発表資料には任意接種は記されないため)
(3)発症期間の問題点等
青野意見書 参照(略)
7審査請求と都道府県の役割
栗原意見書 参照(略)
参考資料(B陳述書に添付)
■第135回疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査会分科会配布資料
https://rieboot.com/0902_%E9%85%8D%E5%B8%83%E8%B3%87%E6%96%99.pdf
■S区予防接種健康被害調査委員会議事録(令和元年7月25日)関連
■熱性けいれんガイドライン
https://www.childneuro.jp/modules/about/index.php?content_id=33
予防接種→単純/複雑型区別なく2,3ヶ月期間を空けることとされている
https://www.childneuro.jp/uploads/files/about/FS2015GL/12fs2015_detail8.pdf痙攣重積
https://www.childneuro.jp/uploads/files/about/FS2015GL/6fs2015_detail2.pdf
複雑型熱性痙攣には脳波検査が必要と書いてある。
■田中真介論文
新潟県MR予防接種被害に係る医療費等の支給申請事案の審査請求に関する鑑定書(略)
*Bさんの裁判については支援の呼びかけをいたします。全国の同時接種後死亡問題に疑問を持っていらっしゃる方の参加も呼びかけます。
(古賀 真子)
厚生労働行政推進調査事業費補助金(公正労働科学特別研究事業)分担研究報告書
ワクチン接種と乳児の突然死に関する疫学調査に関する結果概要
研究分担者 多屋馨子 島田智恵
201906005A202007301648023680011