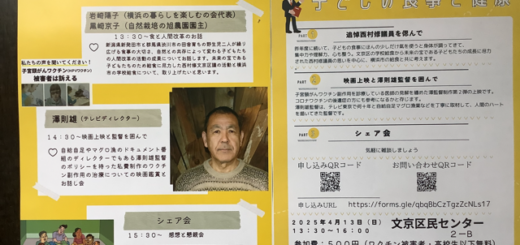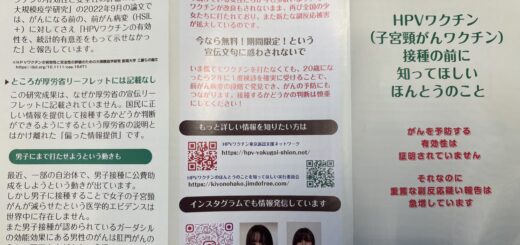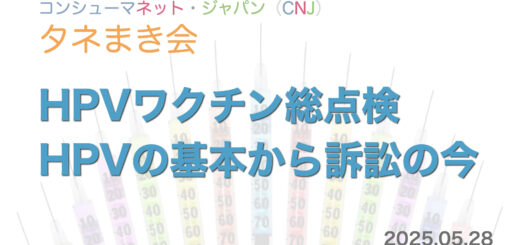赤ちゃんの同時接種 即時見直しを!その2 アーカイブより同時接種死亡事例
ヒブ・肺炎球菌ワクチン同時接種で死亡の女児 審査請求を経て2024年1月26日提訴 その1赤ちゃんの予防接種が急激に増えたのは実はこの14、5年のことです。この間の経緯を簡単に振り返ってみましょう、
2007年ごろから世界のメガファーマーは予防接種をはじめとする医薬品の世界的市場をめぐる販売戦略を進めてきました。2009年の新型インフルエンザ(豚由来)の流行では、流行規模や罹患の重篤さはさほどではなかったのですが、WHOを中心にパンデミック体制が取られました。
新型インフルエンザワクチンがもたらしたもの
使われなかった新型インフルエンザワクチン
2009年にH1N1対策として、新型インフルエンザの国産ワクチン5400万回分(210億円)、輸入ワクチン6700万回分(853億円))を国が買い上げ、のちに国産ワクチンでの副反応による死亡1名が認められました。6700万回分の輸入ワクチンのほとんどは使用されずに廃棄されました(第177回参議院決算委員会2011年5月23日議事録(自民党藤井基之議員の質問)
2020年7月、新型コロナワクチンの開発や輸入で情報が交錯する中、新型インフルエンザの時のワクチン対策を検証するために、阿部知子衆議院銀の仲介で、2020年に母里啓子さんと厚労省担当者に質問しました。
その日の厚労省担当者の回答によると、新型インフルエンザワクチンは当初輸入されたのはグラクソ・スミスクライン社(GSK)の3700万人分、ノバルティス社のものは1200万人分だったと言うことです。しかし、実際の使用実績は約1000人分。つまり4900万人分のうちの1000人分しか使用されませんでした。(0.002%)。残の2000万人分がどうなったのかはいまだに不明です。
この時、新型インフルエンザ特措法(コロナを受け、令和5年政令第261号による改正)とともに、特例承認を受けた製造販売業者に生じた損失を政府が補償するための契約を締結できる、「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法」で損失補償の規定が設けられました。今後も同様の事態が生じた場合に必要なワクチンを海外から確保できるようにしておく必要があるため、平成23年の予防接種法改正で設けられたのです。薬事法で特例承認を受けた輸入ワクチンによる予防接種の健康被害にかかる賠償により生ずる海外メーカーの損失等を国が補償するという契約が法制化されたのです。今回の新型コロナワクチンではこの損失補償法が全面的に適用されています。
返品免除がわりにHPVワクチンの導入?
日本だけでなく片務契約と大量の廃棄は欧州でも起き大きな問題とされました。ワクチンの返品は認められない、いわば緊急事態を盾に返品を認めないという片務契約。日本での2009年の新型インフルエンザ対策に対する検証では、過剰な輸入、廃棄の実態、返品を認めない契約やその後の処理については触れられていません。返品と交換にHPVワクチンの導入がされたという疑惑についてはいまなお明らかにされていません。
https://www.cas.go.jp/jp/caicm/article/feature/backnumber/kako_03.html
一方で、2010年にヒブ、肺炎球菌、子宮頸がん(当時 現在はHPVと言い換え)ワクチンの事業接種(任意接種が始まり、大規模な接種鑑賞が行われました。
HPVワクチンでの甚大な副反応被害はいまなお全国での集団訴訟で争われています。(今後の日程については末尾)
接種勧奨が再開され、新たな被害者が発生する中、9価ワクチンを男児にも勧めることについて反対する声が高まっています。
ヒブ・肺炎球菌ワクチンは必要か
HPVワクチンと一緒に事業接種から定期接種化されたヒブ・肺炎球菌ワクチンはどうだったでしょう。
ヒブ・肺炎球菌ワクチンの導入経緯は
ヒブとはヘモフィルス・インフルエンザ菌・b型の英語の頭文字をとってHib(ヒブ)と言います。ヘモフィルス・インフルエンザ菌の周りに特殊な膜である莢膜(きょうまく)があるものとないものがあります。莢膜のないヘモフィルス・インフルエンザ菌h普通に人の身体の中にもあり中耳炎や副鼻腔炎を起こしますが、莢膜があると白血球に対応されず生き残ります。a〜f型まであるなかで、b型が一番病原性が高く乳幼児が感染・発病すると細菌性髄膜炎を起こすとされます。
肺炎球菌も莢膜を持つ菌です。100種類以上あり髄膜炎や菌血症の原因となります。大人がかかると肺炎になりやすいですが、子ども特に2歳未満では脳を包む膜に入ると細菌性髄膜炎を起こすことがあります。
ヒブも肺炎球菌も常在菌です、生後半年以降はインフルエンザ菌も肺炎球菌も20〜50%が感染し、しばらく保菌して消失します。多くのタイプがあるためにしばらく保菌しては消えていきます。多くの子どもが集団生活で感染し、鼻炎や副鼻腔空炎にかかりながら成長していきます。敗血症や肺炎、髄膜炎、慢性の炎症を起こすかは栄養状態や環境、同居者の喫煙や強い解熱剤の影響などが大きいとされています。高齢者の肺炎の原因であるインフルエンザと肺炎球菌が定期の予防接種(B類型)とされているのは肺炎防止(直接の死因)のためですが、変化し続ける常在菌にワクチンが効くのかは母里啓子さんが常に疑問を呈していたところです。
肺炎球菌は当初ニューモバックス(23価)が使われていましたが、もともと脾臓を摘出された人などtくべつに肺炎球菌性肺炎の危険性の高い人に厳しい制限付きで使用が承認されていました。副反応が多いためです。2009年には健康な壮年の人への効果は疑問とされ、死亡率の低下も期待できない。その他の種類の肺炎にかかるリスクの方が大きいともされている。
しかし、日本ではインフルエンザと肺炎球菌(7価に変更)は高齢者の定期接種B類型とされており、特に施設などでは接種が強制的となっている。加えてコロナワクチンのブースター接種も勧奨されている。元々水ぼうそうウイルスを持っている高齢者にも帯状疱疹ワクチンが強力に勧められている。
子どもの予防接種は何を打つべきか
現在、厚労省は子どもの予防接種については以下のように説明しています。どれも打たなければならないと思わせる内容です。30年前には0歳代のワクチンはBCGと3種混合ワクチン、生ポリオワクチンくらいでしたが、海外製のワクチンの大幅な導入で1年間に10数回接種に行かないと間に合わないようになっています。
ヒブと肺炎球菌、導入時に日本では必要性が低いとの議論もありましたが、過密スケジュールの中で同時接種が当たり前となりました。
次回はヒブ肺炎球菌の同時接種後重度の障害児となったお子さんと2024年1月26日に審査請求での棄却を受けて提訴したヒブ肺炎球菌で死亡したお子さんの事例を紹介いたします。
古賀真子