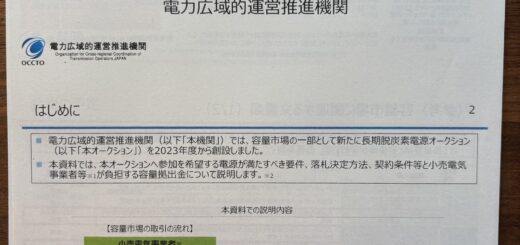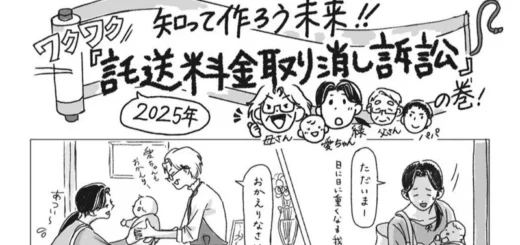アーカイブより 電力託送料金問題を振り返る その1
電気料金と託送料金について パブコメ募集締め切り迫る レベニューキャップ制度や配電事業規制はどうなる?
2021年12月15日に総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 持続可能な電力システム構築小委員会(以下、構築小委)第三次中間取りまとめ(案)に基づき、電力・ガス取引監視等委員会においてレベニューキャップ制度の詳細設計についてのパブコメ募集が始まりました。2020年2月に議論の中間取りまとめがされ、2020年6月、電気事業法の改正を含む「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(以下「エネルギー供給強靱化法」という。)が成立しました。
その後、構築小委は、改正法に基づき、各制度の詳細設計を行うため議論を再開し、2021年8月、第二次中間取りまとめ(2021年8月)を行いました。具体的には、改正電気事業法の施行に向け、送配電網の強靱化とコスト効率化を両立する託送料金制度改革(レベニューキャップ制度)や電源投資確保のための長期的な予見可能性を与える制度措置等について更なる検討を行った他、2022年度に施行予定の配電事業制度の詳細設計等について取りまとめがされました。
第二次中間取りまとめを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会においてレベニューキャップ制度の詳細設計が取りまとめられ、本小委員会において報告されたことから、その内容を中心として、「第三次中間取りまとめ」が出されました。
具体的には、改正電気事業法の施行に向け、送配電網の強靱化とコスト効率化を両立する託送料金制度改革(レベニューキャップ制度)や電源投資確保のための長期的な予見可能性を与える制度措置等について更なる検討を行った他、2022年度に施行予定の配電事業制度の詳細設計等について取りまとめがされました。
第二次中間取りまとめを踏まえ、電力・ガス取引監視等委員会においてレベニューキャップ制度の詳細設計が取りまとめられ、本小委員会において報告されたことから、その内容を中心として、ここに本小委員会の「第三次中間取りまとめ」を取りまとめがされ、パブリックコメントが募集がされています。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620211215&Mode=0
電気料金とは
2016年4月の電力小売全面自由化以前は、自由化されていない一般家庭などに提供される電気料金は政府による認可(規制)が必要とされてきました。1しかし、全面自由化以降は一般家庭にも、政府による認可を受けない小売事業者が自由に設定した自由料金の提供も行われています2。ただし、自由料金に含まれる費用のうち送配電に関わるもの(託送料金)など一部は、事業者間の競争条件を平等にし、安定的な電力供給を行うためにも引き続き政府による認可が必要とされてきました3。
電力自由化前は、電気料金が家計に及ぼす影響が大きいことから、料金改定の際には、経済産業省から消費者庁への協議、さらに、物価問題に関する関係閣僚会議への付議が必要とされていました。また、その際、消費者委員会は同庁からの付議に応じて意見を発出していました。他方、電力小売全面自由化後の託送料金の認可については、消費者庁への協議等は必要とされないこととなり、自由化後も続く託送料金の独占的な位置付けについてはどうなるのかが注目されていました。
電気料金と託送料金
完全自由化前には、託送料金は電気料金に包摂されていましたのでその算定についてはあまり注目されずにきたと思われます。託送料金は一般送配電事業者が維持・運用する電線路を介することに係る基準供給託送料金と、電力量調整に係るインバランス料金がありますが、電力自由化で電気料金が自由化されてからは、2016年に策定された一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則に基づき、総括原価方式により各電力会社(一般送配電事業者)が託送料金を算定して申請(届出)を出すと、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第18条第1項に定める託送供給等約款に基づき、一般送配電事業託送供給等約款料金審査要領に従い審査され、経済産業大臣が認可を行ってきました。
総括原価方式とは
電気料金も託送料金も原価算定に際しては、公益的観点から原価主義規制の中で代表的なものとして、小売全面自由化以前の電気料金および現在の託送料金で採用されているのが「総括原価方式」です。4。総括原価方式とは,事業者の最大限の経営効率化を踏まえた上で安定的な電力供給に必要となる費用を積み上げ、その費用に事業者の適正報酬(利潤)を加えた額を総原価(事業者の収入)として原価を回収できるように料金を設定する方式です。5この方式は、原価が増えるほど回収される料金、つまり事業者の収入も増え、原価が下がれば収入も下がるため事業者の効率化努力により費用が削減された場合,削減費用分だけ収入も下がることになり、効率化へのインセンティブが低下するとされています。
3.11以降、電力会社の資本欠損による値上げせざるを得ない状況が続く中で、総括原価方式による値上げ方式に批判が集まりました。値上げ、特に複数回の値上げをしたのは原発に主力をおいている電力会社であったために、電力システム改革は再エネの普及と脱原発への志向が高まりました。再エネ普及のためのFITが採用され再エネを主力電力とするエネルギー改革が進むかに見えました。
第一次電力託送料金に関する調査会での議論
託送料金の適正性を確保することは、電気料金の低廉化や小売電気事業者の新規参入や価格・サービス両面での競争や多様化を促すものとされています。消費者の利益に大きく関わるとともに電力小売全面自由化の帰趨にも影響します。
託送料金は、電気料金に転嫁され、最終的には消費者が負担するものであり、家計支出に占める電気料金の割合は38%(2016年統計)とされるなか、決して低いものではありません。
2016年5月20日、消費者委員会は、送配電事業を行う電力会社の託送料金の査定について、消費者利益の擁護・増進の観点からの問題の所在及び改善方法について、内閣総理大臣から諮問を受けました。これを受けて、消費者委員会の、「公共料金等専門調査会」の下に、「電力託送料金に関する調査会(以下、「第一次調査会」という。)」が設置されました。(2016年5月23日、第1回会合を開催し、同年7月15日までに計6回開催)①原価低減の託送料金への反映、②固定費の低圧部門、特別高圧・高圧部門への配分、③個別の原価の適正性の3点につき、改善すべき課題があるとの報告がなされました。主な論点としては、1欧州事例で取り上げた送配電設備の固定費負担(回収)の在り方のほか、 2発電事業者の送配電設備の維持・運用費用の負担の在り方などが挙げられました。固定費の見直しや制御不能な費用についての消費者への説明責任も提言されました。
制御不能費用のうち、租税は原価に入れられるものですが、送配電に直接関わらないのではないかと思われる使用済燃料再処理等既発電費用、電源開発促進税等についてはこれまでも異論が出されました。「使用済燃料再処理等既発電費用、電源開発促進税等については、認可されている託送料金原価の約10%とかなりの負担を占めていることについては、送配電のネットワークに要する費用と区別した形で、原価算定及び料金の明示を行うべきである。また、原価算入されている理由等について、消費者により積極的かつ分かりやすい情報公開を行うべきである。なお、政策的観点からの費用を託送料金で徴収していることについては、消費者の納得を得られるよう努力すべきであり、消費者への過度な負担を求めることにつながることのないよう慎重であるべきである。そして、将来的には、エネルギー政策に要する費用に関する国民の負担の在り方については、別途、議論が必要であると考えられる。また、消費者が、託送料金、使用済燃料再処理等既発電費用、電源開発促進税の費用に関する情報を得られるよう、検針票に記載するなどするとともに、小売電気事業者においても、消費者に分かりやすい形で、託送料金、使用済燃料再処 理等既発電費用、電源開発促進税の費用に関する情報を提供するべきである。」とされました。(電源開発促進税の割合は7.5%、例えば東京電力パワーグリッドの場合、託送料金原価に占める使用済燃料再処理等既発電費の割合は 2.2%あるとされました。)
発電側負担金とは? 託送料金に関する議論
電力システム改革の最終段階である発送電分離が完成するとされる2020年にむけて、経済産業省は、小売電気事業者に情報提供を強く働き掛けるとともに、これまで託送料金は小売事業者または旧一般電気事業者の小売部門のみに課せられ,発電事業者からは送配電設備の維持・運用に関する費用回収は行われてこなかった点を議論するようになりました。「電力システム改革による送配電事業者の法的分離により,送配電設備と発電所の一体的な計画・開発が困難となり,発電事業者が送配電設備の整備などに関する費用を意識せず,発電所の立地を検討し,送配電費用が増大するといったことが懸念される。さらに,送配電設備が最大潮流,つまり発電所の最大発電量をもとに設備構築が行われているため,再エネ電源といった発電量が不安定な電源が増えれば,送配電設備の利用率低下といったことも懸念される。」として、送配電設備の整備・運用費用の効率化を図るため,発電容量課金など発電事業者に対しても一定の費用負担を求めるといったことが検討され始めたのです。
その後、経産省は、欧州と同様,固定費が多くを占める送配電設備費用を今後も確実に回収していくため,基本料金回収率の引き上げといった対策が検討されました。また、発電事業者への「発電容量課金」を行うといったことも検討されるようになりました。 発電容量課金とは,発電所の設備容量(kW)に応じ,発電事業者に送配電設備の維持・運用費用の一部を負担してもらう」というものです。電源の立地場所を考慮した託送料金割引制度(需要地近接性評価割引制 度)が既に導入されているが,新電力の既設電源に限った暫定的な制度であり,今後は本制度の適用範囲の拡大・見直しを行うべきといった意見もだされました。
基本料金回収率の引き上げや発電事業者の負担水準などの詳細については今後検討が進められていくことになるとしつつ、諸外国の事例も踏まえ、安定供給に必要となる送配電設備の維持および長期的な設備投資が行え、かつ電力システム全体のコスト低減を図ることが可能な制度となることが期待されるとされました。また,設備投資と効率化をバランスよく行うには,費用の回収方法だけではなく,送配電事業者の収入をどのように決めるのかといった点も重要であると指摘されました。
第二次電力託送料金に関する調査会での議論
貫徹小委員会が残した方向性と問題点
2016年9月27日、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会(以下、貫徹小委員会)が設置され、2017年2月までに5回の会議が開かれ、中間取りまとめがだされました。この小委員会の目的は報告書をそのまま引用することは長文となりますが、重要ですのであえて引用します。
冒頭「戦後 60年余り続いた我が国の電気事業制度は、東日本大震災やその後の電力需給の逼迫を契機に、広域融通の限界や料金水準の高騰といった課題が浮き彫りとなった。こうした課題を克服しつつ、電力やガス、あるいは供給区域といった市場の垣根を越えた競争が可能となるエネルギー市場を形成すべく、岩盤規制打破に向けたアベノミクスの改革の柱の1つとして、1安定供給の確保、2電気料金の最大限の抑 制、3事業者の事業機会及び需要家の選択肢の拡大を目的とする電力システム改革のための電気事業 法等の抜本改正が 2013 年から 3 段階に分けて行われた。
これらの法改正に基づき、改革の第1弾として 2015年4月に電力広域的運営推進機関(以下、「広域機関」
という。)が設立され、2016年4月に第2弾として電力の小売全面自由化が実現した。改革は始まったばかりであるが、異業種からの活発な新規参入や多様な料金メニューの提供等を通じた競争の活性化など、改革に伴う一定の効果が表れ始めている。
具体的には、2016 年4月から自由化された低圧部門(一般家庭等)では、旧一般電気事業者から新規参入者への切替えに加え、旧一般電気事業者の自社内切替えも合わせると、自由化後半年余りで切替件数は全体の約 6.1%となっている 。また、2016年4月以前から自由化されていた特別高圧・高圧部門においては、2016年7月に新規参入者のシェアが初めて1割を超えた。
今後、改革の第3弾となる2020年の発送電分離に向けて、更なる競争の活性化が期待される中で、今後とも競争を通じ、電気料金の抑制や選択肢の拡大を通じて電力システム改革の果実を国民に広く還元するためには、公正・公平な競争環境を整備することが必要不可欠である。とりわけ、経済合理的な電力供給体制と、競争的な市場を実現していく観点から、取引量が販売電力量の約2%に留まる卸電力取引所の取引を含む、卸電力市場の更なる活性化を一刻も早く進めていかなければならない。
同時に、我が国のエネルギー政策の基本的な考え方は、安全性を前提とした上で、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に環境への適合を図ることである(3E+S)。したがって、電力分野においても、更なる競争促進により経済効率性の向上を図る一方、市場原理のみでは解決が困難な安全性の確保や安定供給、再生可能エネルギーの推進を含む環境適合、更には自由化の下での需要家間の公平性確保といった公益的課題の克服を図る必要がある。
これらの取組は、個別にみると、特定の関係者や需要家にとってメリットをもたらすものがある一方、広く負担を生じさせるものもある。加えて、それぞれの制度は相互に関連しているため、本小委員会での議論に当たっては、特定の措置の是非を個別に議論するだけではなく、その内容や規模、時期といった側面から、全体として整合が取れているかという観点も踏まえつつ、各施策の在り方を検討し、電力システム改革を貫徹するという総意の下、総合的な判断として取りまとめを行った。」
というものです。
具体的には、貫徹小委員会は主に、①ベースロード電源市場、②連系線利用ルール、③容量メカニズム、④非化石価値取引市場の4つの制度に関して、その意義と基本的な考え方、今後更なる検討を進める上での留意事項等について、議論を行いました。
その中で、託送料金について、2つの原発関連費用を上乗せすることが決められ、これに対して識者や消費者団体は強く反発しました。その後、提訴した生協団体もあります。
中間報告では2つの上乗せについてはこう示されています。(以下、図表を除き引用)
3自由化の下での財務会計面での課題として、
.2.原子力事故に係る賠償への備えに関する負担の在り方
(1)経緯・課題
東京電力福島第一原子力発電所(1F)の事故後、原子力事故に係る賠償への備えとして、従前から存在していた原子力損害賠償法に加えて新たに原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下、「原賠機構法」という。)が制定され、現在、同法に基づき、原子力事業者が毎年一定額 の一般負担金を原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「原賠・廃炉機構」という。)に納付している。原子力損害賠償法の趣旨に鑑みれば、本来、こうした万一の際の賠償への備えは、1F 事故以前から確保されておくべきであったが、政府は何ら制度的な措置を講じておらず(=制度の不備)、事業者がそうした費用を料金原価に算入することもなかった。
このような状況の下で、2016年4月に小売が全面自由化され、新電力への契約切替えにより一般負担金を負担しない需要家が増加していることを踏まえ、需要家間の公平性等の観点から、1F 事故前に確保されておくべきであった賠償への備え(以下、「過去分」という。)の負担の在り方について検討を行った。
2)基本的な考え方
1過去分の負担の在り方
従来、総括原価方式の下で営まれてきた電気事業においては、一般の事業と異なり、将来的な費用増大リスクを見込んだ自由な価格設定を行うことはできず、料金の算定時点で合理的に見積もられた費用以外を料金原価に算入することは認められていなかった。これは、規制料金の下では、全ての需要家から均等に費用を回収することとなるため、同じ電気を利用した需要家間では不公平は生じないということを前提として、その電気を利用した時点で現に要した費用(合理的に見積もられた費用)のみ料金原価への算入 を認めるという考え方に基づく。
しかしながら、過去分を小売料金のみで回収するとした場合、過去に安価な電気を等しく利用してきたにもかかわらず、原子力事業者から契約を切り替えた需要家は負担せず、引き続き原子力事業者から電気の供給を受ける需要家のみが全てを負担していくこととなる。こうした需要家間の格差を解消し、公平性を確保するためには、全需要家が等しく受益していた過去分について、全ての需要家が公平に負担することが適当であり、また、そうした措置を講ずることが、福島の復興にも資するものと考えられる。
2過去分の規模
過去分は、原賠機構法が措置されていれていなかったために生じたものであることから、その規模の算定に当たっては、現行の一般負担金の算定方式を前提とすることが適当と考えられる。具体的には、各原子力事業者が納付する一般負担金の額が、各事業者が保有する原子力発電所の設備容量(熱出力 kW)等を基準に決定されていることを踏まえれば、過去分の総額は、現在の一般負担金の額と原子力発電所の設備容量等の関係を基に算出した一般負担金の kW 当たりの単価(1,600 億円÷全事業者の設備容量総和)に、全事業者の累積設備容量(各炉の設備容量×炉年(運開後の経過年数)の総和) を乗じることで算定することができ、この方法で算定される過去分の総額は約 3.8 兆円となる。
3全ての需要家から公平に回収する過去分の額
現在、原子力事業者が毎年納付している一般負担金は、経過的に措置されている小売規制料金等により回収されていることから、全ての需要家からの過去分の公平な回収は、小売規制料金が原則撤廃される 2020 年に開始することが妥当であると考えられる。この場合、2019 年度までに納付される一般負担金は、小売規制料金の残る限定的な競争環境下で回収されるため、全需要家ではないものの、概ね全ての需要家から回収されると考えることができる。
このため、全ての需要家から公平に回収する過去分の算定に当たっては、2011 年度から 2019 年度までに納付される一般負担金を全需要家から回収する過去分と同様のものと扱い、過去分の総額から控 除する。2019 年度までに原子力事業者が納付することが想定される一般負担金は、今後の負担金が 2015 年度と同条件で設定されると仮定すれば約 1.3 兆円であり、これを過去分総額から控除すると、約 2.4 兆円となる。
4過去分の回収方法
小売全面自由化により需要家が電力の供給者を自由に選択できるようになる中で、広く需要家に負担を求める方法は、(a)税・賦課金等のように全国の需要家に一律に負担を求める仕組みと、(b)託送料金の ように特定の供給区域内の全ての需要家に一律に負担を求める仕組みの2つに大別できる。
この点、電源構成に占める原子力の割合(すなわち、原子力の電気の利用量)は供給区域ごとに異なる一方で、過去分の負担は、過去の原子力の電気の利用に応じて行うべきものであることや、現状、一般負担金は小売規制料金に含まれ、供給区域ごとに異なる水準となっていること等を踏まえると、過去分を国 民全体で負担するに当たっては、特定の供給区域内の全ての需要家に一律に負担を求める託送料金の仕組みを利用することが適当と考えられる。
約 2.4 兆円の過去分を託送料金の仕組みを利用して全需要家から回収する場合、単年度当たりの需要家の負担を最大限抑制しつつ、将来世代に過大な負担を課さないようにする必要がある。国内で初めて商 用原発が稼働(1966 年)してから原賠機構法の制定(2011 年)まで45年であり、また、現行規制法上、原発の稼働期間が原則 40 年であることを踏まえると、回収期間を40年(年間回収額 600 億円)とすることが妥当と考えられる。このとき、1kWh 当たりの負担額は 0.07 円(標準家庭(260kWh)での負担は 18 円/月)27となる。
(3)留意事項
今回、検討を行った過去分は、事故への備えの不備により生じた準備不足分について、自由化という外生的要因を契機として一定の仮定の下でその規模を特定したものである。このうち、全ての需要家から 公平に回収する分の総額の上限が 2.4 兆円であり、これは、今後、変動が生じる性格のものではない。
本来、発電部門の原価として回収されるべき過去分について、託送料金の仕組みを通じて広く全需要家 に負担を求めるに当たっては、その額の妥当性を担保する措置を講ずるとともに、個々の需要家が自らの 負担を明確に認識できるよう、指針等を通じ、小売電気事業者に対し、需要家の負担の内容を料金明細票等に明記することを求めていくべきである。
また、原子力に関する費用について、託送料金の仕組みを通じた回収を認めることは、結果として、原子力事業者に対し、他の事業者に比べて相対的な負担の減少をもたらすものである。このため、競争上の公平性を確保する観点から、原子力事業者に対しては、例えば、原子力発電から得られる電気の一定量を小売電気事業者が広く調達できるようにするなど、一定の制度的措置を講ずるべきである。
なお、特定の電源の発電費用の一部について全需要家に負担を求める場合、需要家による小売電気事業者の選択、ひいては需要家の電源選択の自由を損なうのでないかとの懸念もあり得る。しかしながら、 例えば、需要家は、一般送配電事業者がインバランス供給に用いる電源(主に火力電源由来)とは無関係 に、CO2 フリー等の特定の料金メニュー(電源)を選択可能である。つまり、送配電網の利用料たる託送料金は、全ての小売電気事業者が同様に負担する競争中立的なものであり、託送料金に含まれる費用の内 訳により、需要家の電源選択が妨げられることはない。
3.3.福島第一原子力発電所の廃炉の資金管理・確保の在り方
(1)経緯・課題
1F の事故から 6 年近くが経過した今もなお、避難指示は続き、1Fの事故収束も道半ばにある。賠償や除染、廃炉など事故に伴う費用は増大しているが、小売全面自由化の中にあっても事故収束や福島復興の歩みが滞ることがあってはならず、こうした危機感を背景に、東京電力の非連続の経営改革を具体化していくための検討を行う「東京電力改革・1F問題委員会(東電委員会)」が 2016 年 9 月に設置された。
東電委員会から国に対しては、同年 10 月、1Fの廃炉に必要な資金については、東京電力が負担することが原則であり、東京電力にグループ全体で総力を挙げて捻出させる必要があるとの考え方の下、「国民 負担増とならない形で廃炉に係る資金を東電に確保させる制度」について、検討要請がなされた。本小委員会においては、この要請を踏まえ、(a)1Fの廃炉の円滑かつ着実な実施を担保するため、長期間にわ たり必要となる巨額の資金の適切な管理を担保する制度と、(b)発電・送配電・小売に分社化されている東電において、自由化の下でもグループ全体で総力を挙げて捻出する資金が確実に廃炉に充てられるための制度について、検討を行うこととした。
2)基本的な考え方
1確実な資金管理の方策
1Fの廃炉に必要な資金については、東京電力(燃料火力、送配電、小売を含むグループ全体)が負担することが原則である。他方で、世界に前例を見ない 1F の廃炉に必要となる資金は巨額であり、かつ、その 支出は長期間にわたることが見込まれる。このため、巨額の資金を長期間にわたり適切に管理していくため、第三者機関(例えば、原賠・廃炉機構)に、廃炉に係る資金を積み立て、当該機関が廃炉の実施・支出を管理・監督する積立金制度を創設することが適当である。
2送配電事業の合理化分の充当 東京電力によるグループ全体での総力を挙げた経営合理化等で必要な資金を捻出させるに当たり、総括原価方式の料金規制下にある東京電力パワーグリッド(送配電部門、以下、「東電 PG」という。)においては、例えば、託送収支の超過利潤が一定の水準に達した場合、電気事業法の規定に基づき託送料金の 値下げを求められることがあり、合理化努力による利益を自由に廃炉資金に充てることはできない。したがって、東電 PG における経営合理化分を確実に 1F廃炉に充てられるようにするため、毎年度行われる託送 収支の事後評価に例外を設けるべきである。
具体的には、託送収支の事後評価において、東電PGの合理化分のうち、東電PGが親会社(東京電力 ホールディングス)に対して支払う 1F廃炉費用相当分について、(a)超過利潤と扱われないように費用側に 整理して取り扱われるようにする制度的措置、(b)乖離率の計算に際して実績単価の費用の内数として扱われるようにする制度的措置を講ずることが適当と考えられる。
3)留意事項
上記措置を講ずるに当たっては、(a)東電PGの託送料金の値下げ機会が不当に損なわれないよう、東電PG自体の超過利潤・乖離率の代わりに、他の一般送配電事業者の効率化達成状況によって値下げ命 令の要否を判断する、(b)東電グループ全体の中で東電PGの負担が過大なものとならないよう、例えば収 益性や資産状況を参考に、グループ各社との負担の程度を比較し、著しく不適当な分担となっていないか どうかを確認するといった措置を併せて講ずる必要がある。
3.4.廃炉に関する会計制度の扱い
(1)廃炉会計制度について
1経緯・課題
従前の電気事業会計制度の下では、廃炉に伴う資産の残存簿価の減損等により、一時に巨額の費用 が生じることで、(a)事業者が合理的な意思決定ができず廃炉判断を躊躇する、(b)事業者の廃炉の円滑な実施に支障を来す、との懸念があった。このため、2013 年と 2015 年の二度にわたり、設備の残存簿価等を廃炉後も分割して償却(=負担の総額は変わらないが、負担の水準を平準化)する会計制度が措置された。こうした制度整備を受けて、2015年に5基、2016年に1基の原子炉について、廃炉決定が行われている。
廃炉会計制度は、計上した資産の償却費が廃炉後も着実に回収される料金上の仕組みが併せて措置されることを前提としており、現在は小売規制料金により費用回収することが認められている。したがって、現在経過的に措置されている小売規制料金が原則 2020 年に撤廃されることを見据えた場合、今後も制度を継続するには、着実な費用回収を担保する措置を講ずることが不可欠となる。この点、2015 年3月の廃炉に係る会計制度検証ワーキング・グループ報告書(「原発依存度低減に向けて廃炉を円滑に進めるため の会計関連制度について」)においては、競争が進展した環境下においても制度を継続させるためには、「着実な費用回収を担保する仕組み」として、総括原価方式の料金規制が残る送配電部門の料金(託送料金)の仕組みを利用することとされている。
このような中、2016 年 4 月に小売全面自由化が行われたことを踏まえ、今回、廃炉会計制度の継続に係る具体的な制度設計について検討を行うこととした。2基本的な考え方 制度創設の経緯・趣旨を踏まえれば、廃炉会計制度は、原発依存度低減というエネルギー政策の基本方針に沿って措置されたものであり、自由化の下においても原発依存度低減との基本方針に変わりはない ことから、本制度を継続することが適当と考えられる。
本制度を継続するために必要となる着実な費用回収の仕組みについては、現在経過的に措置されている小売規制料金が原則 2020 年に撤廃されることから、自由化の下でも規制料金として残る託送料金の仕組みを利用することが妥当である。ただし、発電、送配電、小売の各事業が峻別された自由化の環境下で、 発電に係る費用の回収に託送料金の仕組みを利用することは、原発依存度低減や廃炉の円滑な実施等 のエネルギー政策の目的を達成するために講ずる例外的な措置と位置付けられるべきである。
3留意事項
発電に係る費用については、本来、発電部門で負担すべきであり、託送料金の仕組みを利用して廃炉会計制度を継続することは、制度を適用した事業者と他の事業者との公平な競争環境を損なうこととなる。 このため、競争上の公平性を確保する観点から、制度を適用できる事業者に対しては、例えば、原子力発電から得られる電気の一定量を小売電気事業者が広く調達できるようにするなど、一定の制度的措置を講ずるべきである。
また、送配電事業と直接関係しない費用について、託送料金の仕組みを通じて広く全需要家に負担を求めるに当たっては、対象となる費用の妥当性を担保する措置を講ずるとともに、個々の需要家が自らの負担を明確に認識できるよう、指針等を通じ、小売電気事業者に対し、需要家の負担の内容を料金明細票等に明記することを求めていくべきである。なお、現行の廃炉会計制度においては、事故炉の廃炉を円滑に進めるとの観点から、2013 年に措置された廃止措置資産については事故炉を対象から除外していない。しかしながら、11F の廃炉に要する資金に ついては、東京電力が確保することを原則とし、今般、そのために必要な制度的措置を講ずることとしていること、21F の6基の炉は既に廃炉判断がなされていること、3核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下、「原子炉等規制法」という。)においては、1F は、サイト全体として、廃炉のために特 別な安全管理の措置が必要とされる特定原子力施設に指定されている一方で、実務上、事故により損傷した 1~4 号機と損傷していない 5,6 号機で異なった取扱いをしていること等を総合的に勘案し、1F の 1~6 号機については、新たに講じられる制度的措置の下で円滑に廃炉が行われることを前提に、原則として託 送料金の仕組みを利用した廃炉会計制度の対象から除外すべきである。」引用終わり
東京電力福島原第一発電所で起きた事故の賠償や廃炉費用は当初20兆円を超えるとの試算されましたがその後も増大し続けています。貫徹委員会はいわば荒技とも言える方法で託送料金で増大し続ける費用を安定的に広く徴収するという発想を、本来厳格な認可手続きを経て決定される託送料金制度に入れ込んだものと評価できます。中間報告を出したものの、その後の議論は最終結論は結果的に他の審議会に委ねることとなりました。
第二次電力託送料金に関する調査会での議論
2度目に設置されたのは託送料金の上乗せを実際の審議が開始された第二次電力託送料金に関する調査会(以下、第二次調査会)が始められたのは2020年8月でした。10月からの託送料金改訂を睨んでの調査会でした。
エネルギー庁の審議会においては、レベニューキャップ制度の詳細については、専門的な料金審査に係る内容を多く含むことから、電力・ガス取引監視等委員会の場で検討を進めていくこととされました。
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/kihon_seisaku/denryoku_kaikaku/index.html
総合資源エネルギー調査会基本政策分科会基本政策分科会や令和元年11月から始まった同持続可能な電力システム構築小委員会では「送配電網の強靱化とコスト効率化を両立する託送料金改革」として取り扱われ、詳細設計はWGで議論されています。最終的には先に述べた構築小委の議論を受けての今回のパブコメ募集となったわけです。
託送料金制度の見直しはレベニューキャップ制度についての形式論に終始している
託送料金制度に関する見直しについては、持続可能な電力システム構築小委員会の報告書では「託送料金制度改革や電源投資確保のための制度措置など論点が残されているテーマについて、引き続き検討を深めていくこととともに、電力システムを真に持続可能なものへと深化させるためには、相互に深く関連する電力供給体制や電力市場全体を、各事業者の役割・責任も踏まえ、総合的に検討していくことが極めて重要である。」としており、託送料金に実際に何を原価算定要素として入れるかについての明言を避けています。
一方で、持続可能な電力システム構築小委員会の資料にはレベニューキャップについての具体的な導入のプロセスが示されています。
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_electricity/pdf/0001_03_00.pdf
しかし、原発関連費用は完全にスルーされた状態です。
新しいレベニューキャップ制度の導入が固まり、202年以降は託送料金に関する制度は大きく変更されることになります。内閣府の託送料金等専門調査会で指摘した「外生的な費用や効率化が困難な費用を制御不能費用と位置付けて、託送料金に反映することはやむを得ない措置であるが、公租公課等のほかにどのような項目を制御不能費用の対象とするかについては、十分な検討を行った上でその範囲を明確化し、安易に託送料金への反映が行われないよう特に留意すべきである。」という指摘に関して、経産省のWGどのような結論を出したのでしょうか。
託送料金への上乗せ支払い開始
2020年10月からは実際に託送料金の上乗せが開始され、私たちは2つの問題とされた上乗せ分については小売事業者への電気料金として支払いをする立場に置かれています。((本来は使用済燃料再処理等既発電費の終了による値下げがされるべきでしたが、2020年10月、従来から値上りにならない額までは5社とも上乗せを行いました。4社は値上げにならなかったため、全額を上乗せしました。)
単に取りやすいからと言って、託送料金に「政策コスト」や「制御不能費用」という名目で原発の後始末と言える政策ミスとも言える費用を消費者に一律に負担させて良いものか、今一度問い直すべきではないでしょうか。2021年11月の電気新聞によれば、電力・ガス取引監視等委員会の料金制度専門会合(座長=山内弘隆・一橋大学大学院特任教授)の下、新たな託送料金「レベニューキャップ制度」について、詳細設計の大枠に基づき、料金制度ワーキンググループ(WG)が設置されていますが一般送配電事業者の料金審査が2022年4月から始まる予定とされています。今回の総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 持続可能な電力システム構築小委員会のパブリックコメントはこれまでの議論を集大成し電気事業法改正につなげるものです。
(注)
1 わが国の電力小売市場は,1999 年に特別高圧需要家(契約電力 2千kW以上,2万V 特別高圧系統以上で受電)を対象とした部分自由化が導入され,自由化対象となった需要家には政府による認可を受けない電気料金(自由料金)が提供されてきた。その後,自由化範囲は段階的に広がり,2005 年には日本全体の販売電力量の約6割に相当する高圧需要家(契約電力 50kW以上)以上が自由化の対象となっていた。
2 消費者保護の観点から,自由化後も旧一般電気事業者は2020 年を目処とした経過措置期間終了まで政府により認可された電気料金(規制料金)の提供が義務付けられる。
3 託送料金が引き続き政府による認可が必要となる背景には,送配電部門が自然独占性を有し,複数の事業者による重複投資の回避などを目的に,発電・小売部門の自由化後も引き続き,政府の規制下におかれているといったことも挙げられる
4規制需要家に適用される電気料金については、電気事業法第19条に基づき、電力会社から料金改定の認可申請が提出された場合において、経済産業大臣が審査を行い、広く一般から意見を聴取する公聴会 (電気事業法第108条)等を行った上で、認可を行う。
5規制需要家の料金を定める供給約款の認可基準としては、電気事業法第19条において、「料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること」、「特定の者に対して 不当な差別的取扱いをするものではないこと」等が規定されている。
6(原価等の算定)
第三条 一般送配電事業者は、託送供給等約款料金を算定しようとするときは、四月一日又は十月一日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2 原価等は、次条の規定により算定される営業費、第五条の規定により算定される事業報酬及び第六条の規定により算定される追加事業報酬の合計額から第七条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。
(古賀 真子)
参考
【論文】「廃炉時代」がやってきたー原子力発電の後始末
- 大島 堅一(おおしま けんいち)
龍谷大学政策学部教授 - 2021年12月2日
- 月刊『住民と自治』 2021年9月号より
原子力発電開始後55年たった日本は、原子力発電施設の廃炉と放射性廃棄物処分の課題に直面しています。本稿では、原子力発電の後始末事業の現状を批判的に検討します。
永久に続く終わりの始まり
日本において原子力発電所(以下、原発)の運転が初めて開始されたのは1966年の日本原子力発電(日本原電)東海発電所です。その後1970年に日本原電敦賀1号機、関西電力美浜1号機、1971年には東京電力福島第一原発1号機が運転開始しました。その帰結として、運転開始後ちょうど40年目に、東京電力によって福島第一原子力発電所事故(以下、福島原発事故)が引き起こされました。
福島原発事故後、原子力発電は大きく衰退し、発電電力量に占める原子力の割合は2018年度に6・2%にまで急落しました。もはや原子力発電は基幹電源でもベースロード電源でもありません。事故後に廃炉決定した原発は21基(事故前の3基と合計して24基、実験炉、実証炉を含めて26基)にものぼりました。その結果、2021年7月時点で再稼働および設置変更許可を得た原発と新規制基準審査中の原発の合計(建設中除く)は24基、2499万キロ㍗にまで落ち込み、ピークの4958万キロ㍗(2003~2007年度)の約5割になっています。そのうち、再稼働にこぎつけた原発は、関西電力、九州電力の9基(874・5万キロ㍗)にすぎません。
福島原発事故後、再稼働を進めるとしたものの、追加的安全対策に1基当たり約2200億円の費用がかかっており、運転期間が少なくなっていることもあって既設炉すら経済性がなくなっています(大島、2021)。好むと好まざるとにかかわらず、原発は次々と廃炉になり、原発ゼロ社会は近い将来必ず到来します。原子力発電の後始末事業の始まりです。
後始末事業の区分
原子力発電は、放射性物質を大量に使用するという特徴をもっています。それゆえ、運転中だけでなく、運転前のウラン採掘、核燃料製造過程、さらには運転後の放射性廃棄物処分が必要です。原発が全て運転終了したとしても、原子力発電による問題が終息するわけではありません。その後、廃炉と放射性廃棄物処分が適切に行われなければなりません。
原発廃炉には20~30年の期間を要し、その後も放射性廃棄物処分には非常に長い時間がかかります。最も深刻な問題として取り上げられるのが高レベル放射性廃棄物処分です。高レベル放射性廃棄物がウラン鉱石なみの放射能レベルになるまでの期間は約10万年です。
期間の長さからすると、発電そのものではなく、後始末事業こそが原子力発電の本体事業です。後始末の観点から見ると、短期間の運転とわずかな電気と引き換えに、過酷事故が発生した上に、超長期の手間と膨大なコストを要します。原子力発電の不合理さと無責任さを表すのが後始末事業です。
原子力発電の後始末事業を整理したのが表です。これに見るように、日本の後始末事業は、事故を起こしていない施設(原発や核燃料サイクル関連施設)と事故を起こした施設(福島第一、第二原発)の2つに区分されます。後述するように、事故処理と事故由来廃棄物処分を行わなければならないのは日本の特徴で、すでに次世代は、膨大な負の遺産処理を行わなければならないことが運命づけられてしまいました。
表 原子力発電の後始末事業の全体像
事故の後始末事業は、さらに発電所敷地内(以下、サイト内)と発電所敷地外(サイト外)に区分されます。放射性物質汚染という点では同じであるにもかかわらず、政策の枠組みが異なるため複雑になっています。
事故を起こしていない施設での後始末事業
事故を起こしていない施設の課題は、廃止措置(以下、廃炉)と放射性廃棄物処分です。廃炉は、原子力発電所であろうが、核燃料サイクル施設であろうが、必ず行わなければなりません。原子炉の場合、廃炉に要する期間は20~30年程度とされています。例えば四国電力伊方発電所1号機の場合は30年計画です。
しばしば話題になる廃炉費用は運転期間中に積み立てられます。原子力事業者は廃止措置方針を策定、公表することになっており、現在は、廃止措置費用も含めてインターネット上で見られます。これらの資料を基礎に廃炉費用を全て集計すると約4・2兆円になります。しかし、この費用には収まりません。
例えば、国が開発し、2016年12月に廃炉が決まった高速増殖炉もんじゅの廃炉費用は、原子力規制委員会の認可を受けた廃止措置計画では1500億円とされています。しかし、これには維持管理費2250億円が含まれていません。さらに、人件費や固定資産税、ナトリウムの処理・処分費用が含まれていないため、最低限3750億円はかかります(会計検査院、2018)。同様のことが他の原発にもある可能性があります。
また、4・2兆円には再処理関連施設の廃止費用が含まれていません。再処理計画は常識を超えるもので、運転期間40年間が終わると約40年ほどかけて廃炉されます。これまで再処理工場は操業開始時期が25回延期されました。日本原燃によれば2022年度上期に稼働するといいます。仮に2022年度に稼働したとすると廃炉開始は2062年度、さらに廃炉が終了するのは2102年度あたりになります。再処理工場は、2006年にアクティブ試験をしてしまったため、すでに人が近づけないほどの放射能レベルに達する箇所があります。再処理工場解体は困難を極めるでしょうし、放射性廃棄物処分も解体後の2100年代以降になるでしょう。再処理を含む核燃料サイクルは1960年代に構想されたものです。60年近く前に構想し、後始末を含めて今後100年以上かかるような事業は、日本国内に再処理以外に存在しません。再処理計画は、荒唐無稽としか言いようがありません。
事故を起こしていない原子力発電施設の後始末事業の制約は、政府の原子力政策そのものです。現在、次の2つの制約がある結果、根本的対策がとれないまま、時間と費用が浪費されています。
第1に、日本政府は、いまだに原子力発電を進める方針を持ち続けています。原子力発電により事故が現実に引き起こされ、さらには経済性もありません。今後、民間企業としての電力会社が原子力発電への投資を大規模に行うとは考えられません。にもかかわらず、政府が方針を変えないために原発廃止に向けた建設的議論ができないでいます。原発がどの程度維持されるかによって、放射性廃棄物の処分量は大きくかわります。このままでは、後始末事業についてまともに検討されないまま、次の世代に先送りされてしまうでしょう。
第2に、使用済核燃料の再処理計画が続けられています。問題は、再処理が維持される場合と維持されない場合とでは、日本全体の放射性廃棄物の種類や量が大きく異なることです。技術的にも経済的にも再処理が行き詰まるのは明らかです。本来であれば、再処理を前提とせず、使用済核燃料の直接処分が具体的に検討されるべきです。ところが、ここでも再処理政策の変更が行われないために先に進めなくなっています。このまま推移すれば、再処理政策の破綻が現実化する数十年先に問題が先送りされます。
事故を起こした施設の後始末事業
事故を起こした施設の後始末事業は、サイト内とサイト外で区分されています。もともと汚染源は事故を起こした原子炉で共通しています。ところが、福島原発事故の場合、サイト内とサイト外では適用される法制度が異なっています。また後始末事業の実施主体が分かれており、責任関係も統一性がありません。このことが福島原発事故の後始末を非常に複雑にしています。
サイト内については、原子炉等規制法にもとづく規制と監視が行われています。福島第一原発は、原子力規制委員会によって2012年11月に「特定原子力施設」に指定されました。これにより、東京電力は、瓦礫や汚染水等による敷地境界における放射線被ばくの実効線量を2013年3月までに年1ミリ未満にしなければならなくなり、放射性物質の移動に関して厳しく規制されています。
一方、サイト外の汚染については放射性物質汚染対処特措法が2011年に定められ、同法にしたがって除染や、廃棄物および除去土壌の処分が環境省によって進められています。概して、サイト外のほうが基準は緩く、一種のダブルスタンダードが生まれています。
一例を挙げると、例えばサイト内(ないし放射性物質汚染対処特措法の対象外の日本全国各地)では、放射性セシウムであれば100/キログラム以上は放射性廃棄物として管理、処分しなければなりません。他方、サイト外では、8000/キログラム以下の廃棄物は通常の廃棄物として処分可能とされています。加えて、8000/キログラム以下の除去土壌(除染によって剥がされた汚染された土壌のこと)は再利用可能であるという方針が環境省によって示されています。本来であれば、除去土壌は低レベル放射性廃棄物として管理、処分されなければなりません。
福島原発事故の後始末事業に問題をもたらしている原因は、サイト内、サイト外ともに政府の示したスケジュールにもあります。
サイト内の長期方針は、政府の定めた「中長期ロードマップ」(2011年に作成されて以降、数次にわたって改訂されている)に示されています。「中長期ロードマップ」では、事故後30~40年で廃止措置を完了させるとしています。仮にこのスケジュールを守ろうとすれば残された時間は20~30年しかありません。事故を起こしていない原発でも20~30年かかるのですから政府のスケジュールは達成不可能です。
現時点で総額21・5兆円(賠償を含む)とされている事故費用は今後青天井になるでしょう。なぜなら放射性廃棄物の量が膨大であるからです。日本原子力学会福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(2020)によれば、事故由来の放射性廃棄物量は、重量ベースで、事故を起こしていない大型原子力発電所を廃炉するケースの1000倍以上あります。この処分費用は計算されていません。
サイト外も同様です。除染で発生した除去土壌や汚染廃棄物の多くは、中間貯蔵施設に送られます。国の方針では、中間貯蔵開始後、30年以内に福島県外で最終処分するとしています。しかし、最終処分の具体的方針はなく、費用計算もされていません。そこで、環境省は本末転倒な方針を示しています。すなわち、最終処分場を県外に整備することが困難であるため、最終処分量を減らすとして、福島県内で除去土壌(汚染された土壌)を最大限再利用しようとしています。つまり除染で剥がした土壌を再び土壌として埋め戻すというわけです。この件は、なし崩し的に既成事実化が進められており、除去土壌を用いた農作物栽培の実証事業が環境省によって行われています。
廃炉の時代に
原子力発電の負の遺産の処理には、高レベル放射性廃棄物を含めれば10万年を超える時間と、最低数十兆円の費用を要します。原子力発電による利益を享受した主体は、その利益とは全く関係のない次の世代に、自らが解決できない課題を引き渡そうとしています。原子力発電によってもたらされた負の遺産は取り返しのつかないものばかりです。
原子力発電は、後始末事業という観点から見れば、極めて不公正で倫理に反しています。負の遺産処理は、広範な人々に超長期にわたって影響を与え続けるだけに、公正かつ透明な民主主義的意思決定に基づき決定される必要があります。
【参考文献】
- 大島堅一編(2021)『炭素排出ゼロ時代の地域分散型エネルギーシステム』日本評論社
- 会計検査院(2018)「高速増殖原型炉もんじゅの研究開発の状況及び今後の廃止措置について」
- 日本原子力学会 福島第一原子力発電所廃炉検討委員会(2020)「国際標準からみた廃棄物管理─廃棄物検討分科会中間報告─」
- 2021年12月2日
- 月刊『住民と自治』 2021年9月号より
- 大島 堅一(おおしま けんいち)
- 龍谷大学政策学部教授
原子力市民委員会座長、日本環境会議代表理事。主著に『炭素排出ゼロ時代の地域分散型エネルギー』(日本評論社、2021年)、『原発のコスト』(岩波書店、2011年、大佛次郎論壇賞受賞)など。
![]()