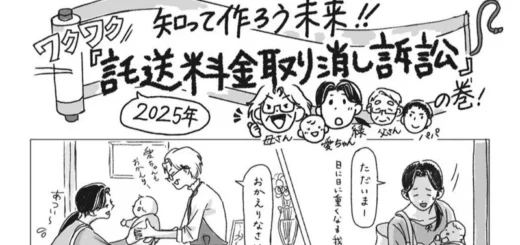託送料金訴訟は電力政策の本質的問題をえぐるものに!! 2.26福岡高裁判決に注目を
3.11を経て、グリーンコープ生協共同体(グリーンコープ)はいち早く支援物資を遠く九州から福島に届けていました。グリーンコープは九州を起点に事業を営む組合事業体です。30余年にわたる脱原発運動の一つの到達点として、「生活に必要な電気を自分たちでつくる」発電所事業と「原発フリーのグリーンコープでんき」の小売事業に踏み出しました。(HPの冒頭にはこうあります)
「二つの事業を進めていく中で、「託送料金問題」と向き合うことになりました。本来入るべきではない原発を維持するための費用(電源開発促進税・使用済燃料再処理等既発電費)、そして2020年10月から「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」が託送料金に上乗せされています。グリーンコープはその託送料金になぜ原発関連の経費が上乗せされるのか、2016年から検証を続け、やはり「原発関連経費の託送料金上乗せは、おかしい」と考え、経済産業省やグリーンコープのエリアの大手電力会社を尋ねて、私たちの要望やお願いを届けました。しかし、理解は得られず、最後の手段として裁判に訴える道を模索してきました。2年半にわたる組合員検討を経て、2020年2月12日にグリーンコープ共同体臨時総会を開催し、「託送料金訴訟」に踏み出しました。」
コンシューマネット・ジャパンでは電力システム改革問題に取り組む一環として、2014年ごろから福岡を起点に西日本で食の安全や環境問題に取り組むグリーンコープ生協と共にこれからのエネルギー政策について考え、行動する研究会で議論を重ね、2016年に託送料金に2つの原発関連費用を上乗せすることについての提訴に向けて行動してきました。
2月26日の判決は勝敗訴にかかわらず、市民が国の政策のとりわけ生活の必需財であるエネルギー供給、電気料金を決定する国の政策のどこがおかしいのか。制度設計に大きく関わった審議会の長やエネルギー(コスト)について研究を重ねている有識者、そして会計学の原則にまで遡って、精緻な訴訟での主張を展開してきた意義はかけがえのない財産です。折しも電力システム改革の検証という名の幕引きのもとに第7次エネルギー基本計画のパブリックコメントがされ、地球温暖化対策計画や温室効果ガス削減、除染による汚染土対策などのパブコメも矢継ぎ早に行われています。「経済成長と脱炭素」を標榜するGX(Green Transfomation)の名の下に、3.11被害の処理は進まず、復興の道は遙です。国に都合の良い国民にツケを回す政策を託送料金訴訟を知り、知らせることが大切です。
控訴審判決が2025年2月26日に出されます。グリーンコープの取り組みと経緯についてこの訴訟の中核として動いてきたグリーンコープ共同体の東原晃一郎さんに寄稿していただきました。
2月26日は “託送料金訴訟” 控訴審 判決日です!
グリーンコープ共同体 東原 晃一郎
「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を経済産業省令によって託送料金(電気料金)に上乗せすることは違法である!
「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を託送料金に上乗せすることを認可した、託送料金変更認可決定の取消しを求めて提訴(同種訴訟として初めて)!

私たち、沖縄県以外の九州各県、中国地方各県、兵庫県、大阪府、滋賀県、福島県の1府15県で事業を営むグリーンコープ生活協同組合が設立した、小売電気事業者である一般社団法人グリーンコープでんきは、2020(令和2)年10月15日、「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を託送料金(電気料金)に上乗せすることを認可した、託送料金変更認可決定(処分庁 経済産業大臣)の取消しを求める行政訴訟を、福岡地方裁判所に提起しました。
ここまでを振り返って
この訴訟は、「わたしが生きることに関わる決定を、わたしの意思によらず、他者がすることは認められない」という、グリーンコープがもっとも大切にすることに基づくものでした。つまり、「賠償負担金」(原発事故の賠償費用)も「廃炉円滑化負担金」(原発廃炉を進める費用)も、そうした負担金を新たに設ける必要があるかないか、あるとしたとき原子力発電事業者ではない全国の新電力事業者とその利用者である国民が負担すべきものであるのかどうか、それを決めるのは今を生きており、未来をつくる自由と責任をもっている国民自身であり、その国民が選んだ国会であって、国民が選ぶことのない経済産業大臣や経済産業省の役人がそれをするのは間違っている、というものでした。

一審判決は、そうした社会と法律、いわば主権者と主権者から業務やときに権限を委託される者の関係の根幹にかんする判断から逃げ、国が主張した「賠償負担金や廃炉円滑化負担金は、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用である」をそのまま採用し、「だから、(電気を利用する国民が一様に払う)託送料
金に含め」得る「適正な原価」となる、したがって、「これら賠償負担金や廃炉円滑化負担金を含む託送料金に変更するという約款を認可しても違法ではない。」と判示しました。
これに対して私たちは、社会と法律、いわば主権者と主権者から業務やときに権限を委託される者との関係の根幹について、その是非判断を、なんとしても裁判所にやってほしいと考えました。そして、そのためにどうしていくか。第一審で根幹に関する是非判断への審理に集中すべく、あえて私たちから主張しなかった、そして判決が基礎においた「賠償負担金や廃炉円滑化負担金が電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用である」に対して、控訴審では「これらは公益的課題に要する費用ではない」ことを明確に立証していくことにしました。
加えて、電力自由化の開始に当たり、託送料金制度がつくられた1999年(平成11年)にさかのぼる審議会報告に始まって今日まで、電力自由化と託送料金制度の設計がどのようにされてきたかを克明に当りなおす作業を志しました。
そうしたことに基づいて、電力ガス取引監視等委員会初代委員長を務めた八田達夫さんの意見書(2023年9月19日第1回期日及び2024年11月27日第6回期日の2つ)、龍谷大学の大島堅一さんの意見書(2023年12月14日第2回期日)、駒澤大学の高野学さん・立命館大学の金森絵里さん・駒澤大学の小栗崇資さん・明治大学の山口不二夫さん4名の意見書(2024年6月5日第4回期日及び2024年11月27日第6回期日の2つ)を提出しました。そうした営為をあわせ、計8つの準備書面を提出しました。
参照
 託送料金認可取消請求事件控訴審経過報告
託送料金認可取消請求事件控訴審経過報告2024年8月28日第5回期日に、初めて国からの準備書面が出されました。うすっぺらに私たちの主張を否定するものでした。どうして「うすっぺら」かと言うと、論拠を示さずに、一審判決をなぞって、だから、控訴審での私たちの主張は否定できるとするものだったからです。換言すれば、控訴審で私たちが提起した幾つかの論点を争点にしたくな
い、裁判官にそれらを考えさせたくないとするものと考えられました。
そうはさせぬと、私たちは準備書面8を最終的に準備しました。八田さんも、会計学の4名の先生方も、もう一度意見を届けることにしました。国は、これらにも反論―反応というが適切でしょうか―しませんでした。二つの見方ができるでしょう。一つは「反論すべき中身も価値もない」と考えていると示さんとするためでしょう。そうした国側の作
戦かもしれません。もう一つは「反論すればするほど問題点が浮き彫りにされていく」のを回避するためでしょう。こちらは真実でしょう。いずれにせよ、国が反論しないと聞き届け、裁判官は「結審」を言明し、来る2月26日に「判決」が出されることとなりました。
判決前に2紙が深堀りした記事を出される気運です。1紙は3つの意見書を軸に、いま1紙はエネルギー政策を巡る昨今の(「原発依存低下」の言葉が消え去ろうと
している)状況との関係でとなるようです。
東京電力福島第一原発の事故処理に関して、次の事実を共有させてください。
2017年に本件2つの負担金制度を決めた際に国が発表した事故処理費用は21.5兆円、そのうち賠償額は7.9兆円であった。2023年末に事故処理費用は23兆円、賠償額は9.2兆円となったと発表された―事故処理費用が増える殆どは賠償額の増というのが現在の特徴。この先、現在8兆円に留まっている廃炉額が青天井に増えていくことが間違いなかろう―。
ところが、それから半年も経たぬ2024年4月公表の別資料(東電と事故処理費用援助を行う原子力損賠賠償・廃炉等支援機構による「第四次総合特別事業計画」)によれば、要賠償額は13.4兆円に増えている。9.2兆円との差4.2兆円はいずれ東電に援助されるはず。半年前の発表の際、こうしたことが分かってもいたはず。
こうした付回しの費用増はちょっと分からないようにされつづけ、一方、国民負担による賠償負担金が投じられるにも拘らず、「事故処理費用は東京電力が責任をもって出し続けます」との虚言が流布しています。判決如何によってそうした虚言の真相も明らかにできるかもしれませんが、何よりも大切なのは、正直な情報公開と意見交換がなされ、事故の処理と対応が行われねばならないことだと思います。
私たちは、2月判決への臨み方と判決後への向かい方を検討しています。グリーンコープ43万人の組合員、この訴訟に目と気持ちを寄せてくれた方々、今とこれからを生きていく国民の皆と、何をどのように共有していけるか、していくかが根っこに置かれることになります。
皆さんが、今を生きる自分たちに関わる一つの光景として、本訴訟のこれからを見届けていただけるよう、心よりお願いを申し上げます。以下に本訴訟の概要をお知らせします。
訴訟の概要
原告:小売電気事業者である、一般社団法人グリーンコープでんき
被告:国(処分庁 経済産業大臣)
請求の趣旨 経済産業大臣が、2020(令和2)年9月4日付けで九州電力送配電株式会社に対して行った託送料金変更認可決定を取り消す。
2023(令和5)年3月22日第一審判決言渡し:原告の請求棄却
同年4月3日、原告控訴
2024(令和6)年11月27日、控訴審第6回期日で結審
2025(令和7)年2月26日、控訴審判決言渡し
内容の概略
電気事業は、自由化によって、発電事業者、送配電事業者、小売電気事業者に分かれている。小売電気事業は完全に自由化されたが、小売電気事業者は、発電事業者から購入した電気(又は自ら発電した電気)を消費者に届けるためには、地域独占の事業体である、送配電事業者に、託送料金を支払って、電気を送配電してもらわなければならない。
送配電事業は、道路などと同様の公共インフラであり、民間業者が営んでいても、強い公的規制のもとにある。託送料金は、「能率的な経営の下における適正な原価」(一般送配電事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価=営業費)に、「適正な利潤」を加えたものでなければならず(電気事業法18条3項1号)、経済産業大臣の認可を受けなければならない(電気事業法18条1項)とされている。
電気事業法施行規則(経済産業省令)等を改正する平成29年(2017年)9月28日制定の経済産業省令は、令和2年(2020年)4月1日以降、託送料金に「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を上乗せして回収すべきとした。
平成29年(2017年)9月28日制定の経済産業省令の定めは、以下に述べるように、違法であり、その違法な省令に基づいて、託送料金に「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」を上乗せして回収することを認可した、経済産業大臣の、令和2年(2020年)9月4日付け託送料金変更認可決定は違法だとして、その取消を求めて提訴した。
「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」とは
国は、「賠償負担金」と「廃炉円滑化負担金」は以下の意味だとしている。
賠償負担金は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「原子力損害賠償法」という。)第2条第2項に規定する原子力損害及びこれに相当するもの(以下、両者合わせて「原子力損害」という。)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が平成23年(2011年)3月31日以前に原価として算定することができなかったもの(電気事業法施行規則(経済産業省令)の2017年(平成28年)改正後の第45条の21の3第1項)
廃炉円滑化負担金は、原子力発電工作物の廃止を円滑に実施するために必要な資金(本件省令による改正後の本件規則第45条の21の6第1項)
経緯
平成23年(2011年)の東京電力福島第一原発事故以来、膨れ上がる福島第一原発事故の損害賠償金をどのようにしてまかなうのか、その後、原子力発電所の廃炉が次々と決まっていく中で、その廃炉にかかる負担をどのようにしてまかなうのかが大きな問題となっていた。今もそうである。
原発事故の損害賠償については、原子力発電をしている電気事業者が賠償責任を迅速かつ確実に果たせるようにするため、原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務づけている(原子力損害賠償法6条、7条)が、その額(賠償措置額)は、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は、一事業所ごとに1200億円である(原子力損害賠償法施行令2条)。
それでは、到底、福島第一原発事故の損害をまかなえない(本件変更認可決定がなされた2020年9月25日現在で、福島第一原発事故の賠償金として、東京電力が支払ったのは、9兆5616億円 ※)。
※ちなみに、2024年4月26日に変更認定された「第四次総合特別事業計画」では、支払った賠償額は11兆2084億円、要賠償額見通しは13兆4179億円となっている。
そこで、国が、事業者に対して損害を賠償するための援助を行う(原子力損害賠償法16条)こととなっており、そのため、原子力損害賠償支援機構(現在の原子力損害賠償・廃炉等支援機構)を設立し、機構が原子力事業者とともに「総合特別事業計画」(損害賠償額の見通し、資金援助の内容及び金額、経営合理化の方策等を記載)を作成して主務大臣の認定を受け、主務大臣の認定後、政府は機構に国債を交付し、機構から原子力事業者に対して必要な資金を援助してきている(2020年9月25日で、9兆3,901億円 ※)。
※これも、2024年4月26日変更認定では、13兆2290億円の交付となっている。
国は、原子力発電事業者が、福島事故前に確保されておくべきであった賠償への備えは約3.8兆円であったとし、そのうち、2019年度までに原子力事業者が納付する一般負担金約1.3兆円を控除し、賠償の備えの不足分の2.4兆円※を「賠償負担金」として、送配電の託送料に上乗せして電気の消費者から回収すべきとした。
※しかしその実は「賠償の備えの不足」ではなく「東京電力福島第一原発事故賠償費用増2.5兆円の対処」のためである。
また、「廃炉円滑化負担金」は、事業者が想定していたよりも早期に廃炉する場合に、設備の残存簿価が一括減損し、一時的に多額の費用が生じることから廃炉判断を躊躇する可能性があったので、「円滑な廃炉を促す環境を整備する」観点から、設備の残存簿価を分割して償却し、その償却分を、電気の消費者から回収すべきとし、2020年7月時点で各原発事業者所有の原発のうち15基分にかかる額を4740億円とした。
(賠償負担金にしても、廃炉円滑化負担金についても、原子力発電事業者が負担すべきものではないか)
本件処分の違法事由
電気事業法施行規則(経済産業省令)等を改正する平成29年(2017年)9月28日制定の経済産業省令によって改正された電気事業法施行規則及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則は、電気事業法の委任の範囲を超え、また、憲法41条にも反する違法違憲・無効なものである。
1 法律に委任規定がないこと
接続供給の相手方(託送受給者)に、賠償負担金の支払い義務及び廃炉円滑化負担金の支払い義務を課すものである。義務を課し、権利を制限することは、法律又は法律の明文の委任によらなければならない。しかし、その支払い義務を課すことを委任する規定は、本件規則への権限を委任する法律である電気事業法には、存在しない。したがって、これらの本件省令の規定は、憲法41条に違反し、違憲であり、無効である。
2 改正後の本件施行規則及び算定規則の定めは委任の範囲を超えるもので違法であること
経済産業大臣は、平成29年9月に改正した、電気事業法施行規則(以下、平成29年9月の改正後、令和4年経済産業省令第24号による改正前のものを「本件施行規則」という。)において、①賠償負担金及び廃炉円滑化負担金を定義(本件施行規則45条の21の3及び45条の21の6)する規定、並びに、②一般送配電事業者が経済産業大臣の通知に従い賠償負担金及び廃炉円滑化負担金をその接続供給の相手方から回収し、回収した賠償負担金及び廃炉円滑化負担金(賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金・本件施行規則45条の21の4第1項三号及び45条の21の7第1項三号)を原子力発電事業者に払い渡さなければならない旨(本件施行規則45条の21の2及び45条の21の5)及び③原子力発電事業者が賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の額について経済産業大臣の承認を受けなければならない旨(本件施行規則45条の21の3及び45条の21の6)の規定等を設けた。
また、経済産業大臣は、同時に改正した、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(以下、平成29年9月の改正後、令和3年経済産業省令第22号による改正前のものを「本件算定規則」という。)において、「一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほか、営業費として、(中略)賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金の額を算定しなければならない。」と定めた。
営業費は、一般送配電事業を営むために必要な費用であり、法18条3項1号で定められている、「能率的な経営の下における適正な原価」に該当するものである。
本件で問題となる、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金は、① 本件施行規則45条の21の3及び45条の21の6において定義された内容、② 本件施行規則45条の21の4第1項三号及び45条の21の7第1項三号に定める通り、一般送配電事業者は全額原子力発電事業者に払い渡さなければならないこと、③ 原子力発電事業者が賠償負担金及び廃炉円滑化負担金の額について経済産業大臣の承認を受けなければならないことなどから明らかなように、一般送配電事業を営むために必要な費用ではない。本来、原子力発電事業者が負担すべきものである。
賠償負担金及び廃炉円滑化負担金は、一般送配電事業を営むために必要な費用ではなく、本来、営業費に該当せず、法18条3項1号で定められている「能率的な経営の下における適正な原価」に該当しない。
営業費にも該当せず、「能率的な経営の下における適正な原価」にも該当しない賠償負担金及び廃炉円滑化負担金を、「営業費として」「算定しなければならない。」とする、平成29年9月の改正後の本件施行規則45条の21の2から7までの規定及び本件算定規則4条2項の規定は、委任の範囲を超えるものであって、法および憲法41条に違反し、違法違憲である。
その他の争点
上記の他、原告(控訴人)に原告適格が認められるか否かについても争点となっているが、第一審は原告に原告適格を認めている。
(関連条文)
電気事業法(昭和39年法律第170号)
(託送供給等約款)
第18条 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び電力量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。以下中略)
3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)
第3条 一般送配電事業者は、託送供給等約款料金を算定しようとするときは、4月1日又は10月1日を始期とする一年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「原価算定期間」という。)を定め、当該原価算定期間において一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業(最終保障供給を行う事業を除く。)の用に供するための電気を発電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「原価等」という。)を算定しなければならない。
2 原価等は、次条の規定により算定される営業費、第5条の規定により算定される事業報酬及び第6条の規定により算定される追加事業報酬の合計額から第7条の規定により算定される控除収益の額を控除して得た額とする。
(営業費の算定)
第4条 一般送配電事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託検針費、委託集金費、雑給、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(その一般送配電事業等を行うために当該一般送配電事業者が使用する電気に係る費用を含む。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、託送料、事業者間精算費、委託費、損害保険料、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法第28条第1項の交付金に相当する額からこれに係る事業税に相当する額を控除して得た額(以下「再エネ特措法交付金相当額」という。)を除く。)、他社購入送電費、振替損失調整額(一般送配電事業者の供給区域内において小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに法第2条第1項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気であって、当該一般送配電事業者の供給区域以外の地域において維持し、及び運用されている発電用の電気工作物の発電に係るものを当該一般送配電事業者が受電する場合に発生する振替損失電力量の調整に要する費用をいう。以下同じ。)、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、電源開発促進税、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るものの額の合計額を算定しなければならない。
2 一般送配電事業者は、前項の規定により算定した合計額のほか、営業費として、使用済燃料再処理等既発電費…、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、賠償負担金相当金及び廃炉円滑化負担金相当金の額を算定しなければならない。
電気事業法施行規則(平成28年経済産業省令第50号)
第45条の21の2 一般送配電事業者は、当該通知に従い、賠償負担金をその接続供給の相手方から回収しなければならない。
2 一般送配電事業者は、第45条の21の4第1項の通知に従い、各原子力発電事業者ごとに賠償負担金相当金を払い渡さなければならない。
第45条の21の3 原子力発電事業(中略)を営む発電事業者(以下(中略0「原子力発電事業者」という。)は、その運用する原子力発電工作物及び廃止した原子力発電工作物(中略)に係る原子力損害(原子力損害の賠償に関する法律(中略)に規定する原子力損害及びこれに相当するものをいう。)の賠償のために備えておくべきであった資金であって、旧原子力発電事業者が平成23年3月31日以前に原価として算定することができなかったものを、一般送配電事業者(沖縄電力株式会社を除く。中略)が行う接続供給によって回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「賠償負担金」という。)の額について、5年ごとに、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第45条の21の5 一般送配電事業者は、当該通知に従い、廃炉円滑化負担金をその接続供給の相手方から回収しなければならない。
2 一般送配電事業者は、第45条の21の7第1項の通知に従い、各特定原子力発電事業者ごとに廃炉円滑化負担金相当金を払い渡さなければならない。
第45条の21の6 (中略)原子力発電事業者(中略)は、当該承認に係る原子力発電工作物(中略)の廃止を円滑に実施するために必要な資金を一般送配電事業者が行う接続供給によって回収しようとするときは、回収しようとする資金(以下この条及び次条において「廃炉円滑化負担金」という。)の額について、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第45条の21の6第2項~第45条の21の7 略
控訴審での私たちの主張(大略)
- 賠償負担金及び廃炉円滑化負担金は、原子力発電事業者の費用であり、一般送配電事業者の費用ではない。それなのに、法律上の根拠なく、一般送配電事業者に、小売電気事業者からの両負担金の徴収義務と原子力発電事業者への払い渡し義務を課す本件省令は違法・違憲であること。 (控訴準備書面8 9~12頁)
- 賠償負担金及び廃炉円滑化負担金は電気事業法18条3項1号の「適正な原価」に該当するのか否か。両負担金は一般送配電事業を営むのに必要な費用でない。託送料金制度を開始した平成11年報告(電気事業審議会基本政策部会報告)の託送料金二原則(託送コストの公正回収・事業者間の公平)に照らしても適正な費用とならない。更に平成28年(2016年)に全面化、令和2年(2020年)に完全化した電力自由化に照らしても、原判決はこの原則を見落としている。(同 14~24頁)
- 原判決の「法は、託送制度を導入した平成11年改正当初から、託送制度において、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用を回収することを想定して」いた事実はなく、その判示は誤りであること。平成11年報告からも、当時の国会審議からもそれがわかる。 (同 25~30頁)
- 原判決が前提とする、電気事業法の平成26年(2014年)改正に際して制度設計ワーキンググループが「小売全面自由化後の託送制度においても、電気の全需要家が公平に負担すべき費用については、負担の公平性や事業者間の競争条件の確保を前提に、託送料金で回収できる仕組みとすることが必要でないか。」と提言した事実はなく、その点の判示も誤りであること。 (同 30~31頁)
- こうした原判決の論拠がなくなったこと及び「一般送配電事業を行うために必要な原価」ではなくても「電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用」を「原価」とできる法文(文理)上の根拠は、何らかの手がかりを含めて示されていないこと。 (同 31~33頁)
- 「送電における公益的課題」と「電力行政一般が実現すべき公益的課題」を混同してはならない。また、前者を超えて、明確な料金算定基準以外の政治的な要因を導入する場合には、国会での政治的論議に基づいた法律に依拠せねばならない。そうした専門技術的検討を超える、政治的な判断を経済産業大臣がするのは、託送料金の算定にあたって経済産業大臣に与えられた権限を超える。この点からも、「一般送配電事業を行うために必要な原価」ではなくても、「電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用」を、法改正なしに「原価」に含められるという法解釈は誤りであること。 (同 34~35頁)
- 同じことは、会計原則との関係からも言える。原価計算基準は慣習法であり、企業会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものである(会社法431条)。そうであるのに、国が一般の会計基準と電気事業会計の「意義や目的が全く異なり、同一視されるべきものではない」と主張することは、会計原則の根幹を揺るがすことである。しかも、その主張は、電気事業会計規則自体の「一般に公正妥当であると認められる会計の原則によって会計を整理すべき」(同規則1条)とも矛盾する。賠償負担金と廃炉円滑化負担金を一般送配電事業の原価(営業費)とする(託送料金算定規則4条2項)のは、本来なされるべき会計と全く異なる会計をすることであり、原子力発電事業者の費用が、一般送配電事業者の費用として決算整理され、有価証券報告書等に期待される機能が果たせなくなる。 (同 36~40頁)
- そして、賠償負担金も廃炉円滑化負担金も、電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用ですらないこと。第一に、原判決が、両負担金が「本件(託送料金)算定規則4条2項の改正により導入された」と認定するのは誤りである。両負担金を定義し、具体的金額の算定・決定方法を定め、誰がどのように徴収し、誰に渡すのかを定めているのは、本件(電気事業法)施行規則45条の21の2~21の7である。 (同 41~44頁)
- 原判決では、廃炉円滑化負担金がそもそも「電気の全需要家が公平に負担すべき電気事業に係る公益的課題に要する費用」であるという理由すら示されていない。発電工作物の廃止は、発電事業者の業務であり、その費用は発電事業者が負担せねばならない。「廃炉会計制度の維持」とか「小売全面自由化の下でも原発依存度低減や廃炉の円滑な実施等のエネルギー政策の目的の達成」とかは、政治的判断の事項で、かつ、電力行政一般が実現すべき公益的課題である。「送電に関する公益的課題」とは関係ない。とりわけ電力自由化のもとでは、この費用は発電事業者が負担すべきであり、そうしないことは電力自由化の目的に反することにもなる。 (同 44~46頁)
- 賠償負担金は、東電福島第一原発事故の賠償費が膨らみ、その不足2.5兆円を穴埋めするために求められ、実際に事故の損害賠償金に充てられるものであり、本来、事故を起こした原子力発電事業者が負担すべきものである。事業者によるこの賠償責任は、世界全体が規範とする「汚染者負担の原則(1972年OECD)」に合致し、原子力損害賠償法(1961年)も公害対策基本法(1967年)もそう定めている。したがって、電気の需要家に賠償負担を課すのは認められていないことなのである。加えて、原子力損害賠償法の規定によれば、国が説明する「賠償負担金は、原子力損害賠償法に基づく原子力損害賠償の資金として備えることができなかった「不足分」である」とする、そうした「不足分」は発生しないのである。 (同 47~51頁)
- 原判決は、平成29年(2017年)国会でこの審議がなされたとするが、これは同年国会経済産業委員会での経済産業大臣の誤った答弁(平成11年電気事業法改正のときに、審議会で、託送料金によって全ての消費者が広く公平に負担すべき費用を回収できるメカニズムを入れていったかのように、事実に基づかない答弁)に引っぱられて誤った結論を導き、判断の基礎となる重要な事実を誤認してしまったものである。 (同 51~53頁)
- 国が主張するストランデッドコスト論(地域独占・総括原価方式が電力自由化に移行したさい、料金回収が保証されていた原価が回収困難となる費用=ストランデッドコストが発生する。アメリカ(ペンシルバニア州、…)、カナダ、…等でその回収の措置が講じられた。それと同じである)は、これが発電所の建設コスト回収の問題であったこと及びそうした要求がされた国・地域固有の問題であったことを抜きに、また、賠償負担金も廃炉円滑化負担金も電力自由化で生じたものでなくストランデッドコストでないことを抜きにするもので、不適切な持ち出しである。 (同 53~55頁)
- 電力自由化の下では電力料金は競争的市場で決定され、原子力発電事業者から電気の供給を受けた場合と、原子力発電事業者以外から電気の供給を受けた場合で、電力料金は基本的に同一である。したがって「(賠償負担金が無ければ、原子力損害の賠償のために備えておくべきであった資金の不足分を)原子力発電事業者から切り替えた需要家は負担せず、引き続き原子力発電事業者から供給を受ける需要家のみが全てを負担する」ということはない。国は、電力自由化後の価格決定が、自由化前の価格決定と全く異なっていることを理解していない。
(同 55~59頁) - さらに国が主張する「原子力発電事業者から電気の供給を受けた場合と、原子力発電事業者以外から電気の供給を受けた場合とで、電力自由化後の電気料金が同一となるようなことがあったとしても、…賠償負担気及び廃炉円滑化負担金を託送回収しないこととすると、原子力発電事業者は、託送供給の有無にかかわらず賠償負担金及び廃炉円滑化負担金を回収する必要があることから、必然的に電気料金の中にこれらを算入せざるを得ず、…原子力発電事業者以外から電気の供給を受けた場合は電気料金の内訳に上記賠償負担金及び廃炉円滑化負担金が含まれないことになるため、原子力発電事業者から電気の供給を受ける需要家とそれ以外から電気の供給を受ける需要家の間に負担の公平性が保てないことになることに変わりがない。」といった状態は、第一に、電力自由化後は、発電事業者に生じたコストはその発電事業者自身が負担する、第二に、電力自由化後は競争的市場において卸売り電力料金は決定され、総括原価方式と異なって「内訳」で価格が決定されるわけではない、第三に、電力自由化の下では、需要家は、誰から電気を購入するかは自由であり、仮に不公平があったら需要家自身が他から購入することで直ちに是正される、という三点によってわかる通り、存在し得ないものである。 (同 59~61頁)
全体のまとめ
(同 61~64頁)
最後に、第一に、本件省令改正は、政府内の一部の声でなされたものであり、それまでの政策とも矛盾し、電力自由化の本質を揺るがす重大な事態である。託送料金制度を開始するにあたってまとめられた電気事業審議会基本政策部会報告(平成11年報告)の二原則「第一原則 託送コストの公正回収原則」「第二原則 事業者間公平の原則」に反し、送配電に必要といえない費用で、一部の発電事業者の費用であるものを託送料金として徴収することとしている。それは、1997年の電気事業審議会の専門委員就任から2015年電力ガス取引等監視委員会初代委員長就任にいたるまで一貫して、電力自由化政策や託送料金制度設計に携わった八田達夫氏が指摘するとおり、それまでの政策と矛盾し、電力自由化の本質を揺るがす重大な事態である。
第二に、本件省令改正は、賠償負担金及び廃炉円滑化負担金という原子力発電者の費用を、一般送配電事業の「原価」として整理することを求めるものになっている。一般送配電事業の売上でも収益でもない託送供給の相手方(小売電気事業者)からの「賠償負担金相当金又は廃炉円滑化負担金相当金」分の入金を収益に計上し、経費(費用)でもない「賠償負担金(相当金)や廃炉円滑化負担金(相当金)」を経費(費用)として計上することになり、それに沿って、損益計算書その他の計算書類が作成されることとなる。本来なされるべき会計と全く異なる会計がなされることとなる。経済のインフラである、会計原則(その事業の原価を公開し、需要家・株主他が識別可能な、公正さを保つもの)、電気事業の企業会計(企業の正確な財務状況を示し、株式・債券・労働・電力市場参加者や電力消費者・地域住民にとって意思決定をおこなう基礎情報を提供するもの)を歪め、会計学の観点からはもちろん、金融商品取引法や会社法上も容認できない結果をもたらす。
以上のようにとんでもない、しかも、文理上、その解釈上の根拠がない、本件省令改定は正すべき必要がある。八田達夫氏の意見書にもある「中立的立場にある私が書いた本意見書は、彼ら(政治的圧力によって合理的な政策形成が歪められるなか、なんとか合理的で適正な政策に転換しようとしている多くの経済産業省官僚)の声を代弁する役割も果たしていると思う。政治から独立している裁判者が、公正なご判断を下さることの意義は、この件においては、とりわけ大きいと信じる」との声を踏まえていただき、裁判所におかれては是非とも公正な判断を下さるのを願う。 (同 65~69頁)
以上