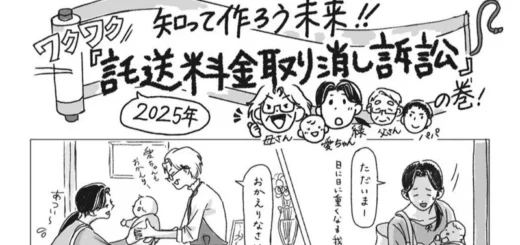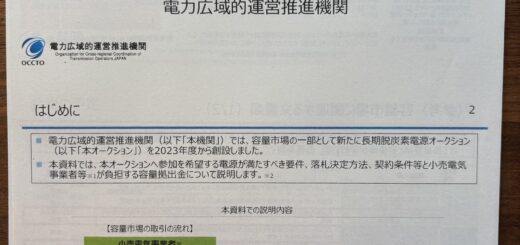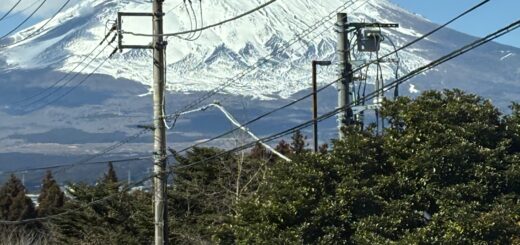第7次エネルギー基本計画は再エネを実現できるのか?
市民団体、消費者団体の間では7次エネルギー基本計画についての学習会が行われています。
計画はざっと見ただけでも、原発の利用や化石燃料へのアンモニアや水素利用など各地流していない技術に期待するもので、海外では主力となった風力発電への取り組みが何周回りで遅れており「再エネ達成目標は困難」なことは火を見るより明らかです。提示されているデータも都合の良いところを切り取った誘導的なものです。

日本では風力が極めて遅れている。太陽光も自然破壊と揶揄されがち。本当のところは?
パブコメを出して
(資源エネルギー庁)第7次エネルギー基本計画(案)に対する意見募集
募集期間:令和6年12月27日(金)~令和7年1月26日(日)必着
エネルギー政策基本法に基づき審議会において議論がなされてきた、第7次エネルギー基本計画(案)に関して、意見を募集しています。
○「第7次エネルギー基本計画(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=620224019&Mode=0
エネルギー政策について、関連して以下についてのパブコメ募集も実施されています。
(内閣官房、環境省、経済産業省)「地球温暖化対策計画(案)」に対する意見募集
募集期間:令和6年12月27日(金)~令和7年1月26日(日)必着
地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、見直しの検討が進められてきた「地球温暖化対策計画(案)」について、意見を募集しています。
○「地球温暖化対策計画(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240104&Mode=0
(環境省)「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(案)」に対する意見募集
地球温暖化対策計画の見直しを受け、政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画の改定案について意見を募集慕います。
募集期間:令和6年12月27日(金)~令和7年1月26日(日) 必着
○政府実行計画「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195240100&Mode=0
(内閣官房、G X 実行推進室、経済産業省、外務省、財務省、環境省)「GX2040ビジョン(案)」に対する意見募集
経済成長と脱炭素の両立であるGX(Green Transformation)の実現に向けた長期の政策の方向性について「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(令和5年7月28 日閣議決定)」を改訂した「GX2040ビジョン(案)」についての意見を募集しています。
募集期間:令和6年12月27日(金)~令和7年1月26日(日)必着
○「GX2040ビジョン(案)」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595224049&Mode=0
2025年1月26日、コンシューマネット・ジャパンとしてパブコメを「提出しました。Foe Japanさんのものを参考にさせていただきました。
第7次エネルギー基本計画(案)への意見
1. エネルギー政策の基本的視点
2. 2040年度電源構成
3. 電力需要
4. 省エネ
5. 1.5℃目標
6. 原子力
7. 火力発電の延命、水素・アンモニアの脱炭素効果
8. 鉱物資源
9. 策定プロセス
1.エネルギー政策の基本的視点
(1)全体的に国際潮流に反し、現実に活用可能な再生エネルギーへの真摯な取り組みを感じられない。
「2050年までにネットゼロ」と題したIEAの報告書は2040年までに先進国で火力発電廃止、2035年までにガソリン車の新車販売禁止などの提言が盛り込まれている。再エネの設備容量が2030年までに3倍、2050年に8倍とし電源構成に占める再エネ比率は2050年には88%に達するという結論である。2024年10月に公表さえた「世界エネルギー展望2024」では2050年に再エネ88.5%、原子力8.7%、火力1.5%水素1.2%と微修正されている。
これに対して、政府案は脱炭素化に最も効果のある自然エネルギー発電を2040年でも4~5割にとどめている。とりわけ風力発電は電源構成の4~8%しか供給しない計画となっている。エネルギー効率改善の不徹底であり最終エネルギー消費の削減は1割程度しか見込んでいない。
3.11以降、化石燃料に対する依存が高まり、その大宗を海外に依存してきたこと、2023年に原油や天然ガスなどの鉱物性燃料の輸入総額が約26兆円にまで達していることは憂うべきであるが、エネルギー需要構造のの転換、政策の再構築に関してのこれまでの国の姿勢は再生可能エネルギーへの政策が順調でなかったとことの証左であり、ましてや原発復帰が現実性がない中で制定されたGX推進法、GX脱炭素電源法は福島への真摯な反省や原発への依存を望む国民の納得を得られたものとは言えず、国民に対する説明が欠如している(該当ページ(以下略)p3)。
(2)2033年度にかけての電力需要の増加想定のもと、脱炭素電源の供給確保に万全の備えを行うために最先端半導体や光電融合技術などの最先端技術やそれを支える液体冷却装置技術などを用いる最先端の付帯設備の活用によるデータセンターのエネルギー効率の改善などの取り組み等が挙げられているが、脱炭素電源の確保はて途上にある新規の脱炭素電源の開発・推進に依拠するよりも、他国の先例を学び風力など足元の再生可能エネルギーの拡大を目指すべきである。日本には2040年に電力の90%以上を自然エネルギーで供給できる十分なポテンシャルがあるとの試算もある。(p9)
(3)第7次エネルギー基本計画案では、S+3Eの一つとして、「環境適合性」を挙げているが(15p)、脱炭素についてしか言及がない。第6次エネルギー基本計画では「エネルギーの脱炭素化に当たっては(中略)エネルギー供給面のみならず、サプライチェーン全体での環境への影響も評価しながら脱炭素化を進めていく観点が重要である」という記載があったが、サプライチェーンへの配慮をどうするか、だ今回の案で記述を削除した理由を明記すべきである。(15p)
(4)気候変動危機や生物多様性危機は、現在のエネルギーの大量生産・大量消費の産業構造は限界を迎えていることを示している。鉱物資源やエネルギー資源などの採掘現場においては、環境破壊や人権侵害が頻繁に生じており、地元の人々の生活を脅かしている。現在のまま、際限のない採掘や消費を継続していくことは、いずれ破綻を招くことは明らかである。
エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーの自国のポテンシャルを冷静に見直し、合わせて、需要削減を最優先させるとの原則を打ち出し、あらゆる分野への働きかけを行い戦略的に実施していくための対策をたてるべきである。(該当箇所:全般)
(5)「脱炭素電源」として原子力と再エネとを区別せずに記述しているが、これを区別し、「再生可能エネルギーの促進」とすべきである。
原子力は、安全性の観点から大きな課題があるほか、既存原発の大半が30年を超えて老朽化している現実や、新規の建設の経済性が見通せないことからも、2030年2割、2040年2割の目安目標のいずれも、現実的ではない。
日本でポテンシャルのある風力は安定的な調整電源にもなりうる。風力や太陽光を大きく増やしていくためには、変動する出力に合わせ、需要やその他電源を柔軟に調整する必要がある。対して、原子力は、火力と比べても出力調整が容易でない電源であるのでベースロード電源的な扱いはやめるべきである。
このように、脱炭素電源といっても原子力の拡大と再エネの拡大は相反するため、それぞれを区別し、原子力はあくまでもゼロを目指し、「再エネ電源」を最優先で拡大させるべきである。(23pほか)
2.2040年度電源構成
(1)案では2040年度原子力2割としているが、これは、再稼働できる見込みがない原発も含め、30基以上稼働させなければならない極めて非現実的な数字である。認可をうけた柏崎刈羽などの3基、未だ審査中の浜岡、泊など7基が再稼働しても不十分である。2040年までに4基が運転期間60年を超えること、建設に20年を要する原子炉の新設はま間に合わないと考えられるが、「2割」の前提として、少なくとも原発何基の稼働ほかを想定しているのか明確に示すべきである。そのことが安易に電力需要の増加や化石燃料の高騰による国富の流出に加え、脱炭素のためには原子力に依拠せざるを得ないとの論調を蔓延させている様であるが、原子力発電の現実をつぶさに国民に説明しないまま、2割という数字が一人歩きして、他のエネルギーへの転換を行わないことこそ、で電気料金価格の高騰を招き国民の生活を圧迫し、国際経済力を減ずるという事実を国民に詳らかにする責任がある。
加えて、原発に関しては、事故の被害やリスク、放射能汚染や解決不可能な核廃棄物の処分の問題などが山積している。経済的にみても、原発の維持費や建設費は高騰し続けており、今や世界的にも最もコストの高い電源となっている。また、原発はトラブルが頻発している上、ひとたび停止すれば広範囲に影響をもたらすこと、調整力に欠けることから、決して「安定」電源とはいえない。あくまでも原発ゼロをめざすべきである。
(該当箇所:エネルギー基本計画案全般、(関連資料) 2040年度におけるエネルギー需給の見通し)
(2)火力3~4割では、国際合意と相反し、1.5℃目標にも整合しない。
COP28ですでに、世界は「化石燃料利用からの脱却」に合意している。またG7では2022年から「電源の大部分を脱炭素化」すること、さらに2024年には「2035年までに石炭火力から脱却」する方向性にも合意している。一方で日本では、石炭火力を含む発電部門の化石燃料利用を継続することが強く主張され、今回2040年の電源構成でも火力を3~4割としており、国際合意に反している。1.5℃目標を目指すうえでも、できる限り早期に大幅な削減が必要である。火力発電は可能な限り削減し、省エネ・再エネに移行しなければならない。
(該当箇所:エネルギー基本計画案全般、(関連資料) 2040年度におけるエネルギー需給の見通し)
3.電力需要
DX(データセンター等)による電力需要増加が、根拠あいまいなまま過大評価され、DXによるエネルギー効率改善等の需要削減効果については全く言及されていない。
デジタル化はデータセンター設置増加等による電力需要の増加をもたらす面もあるが、効率化によりエネルギー需要の低減をもたらす面もある。
第6次エネルギー基本計画においては、デジタル化による省エネルギーを進めることが記述されていた。第7次ではそうした記述がすべて削除されている。
「データセンター」という言葉が、第7次案には16箇所にわたり使用されているが、いずれもデジタル化の進展による電力需要増加を強調する内容である。
政府の総合エネルギー統計(2024)においては、データセンターやIT関係のエネルギー消費は0.46%に過ぎない。政府が引用している電力中央研究所のレポートでも急増や激増とはしていない。世界的にみてもIEAのレポートではデータセンターは増大要因としては大きくない。(p.11ほか)
4.省エネ
(1)省エネルギーによるエネルギー削減目標を明記すべきである。
省エネルギーこそがあるべき電力政策の肝ともいうべきものである。省エネルギーによりエネルギー需要・電力需要をどこまで削減しようとしているのか不明である。2040年度エネルギー需給見通しにおいて、対策をとらなかった場合(BAU)のエネルギー需要、電力需要の予測値に加え、省エネルギーによる削減の方途を真剣に探るとともに削減の見込みを明記すべきである。
(2)省エネルギーの内容が具体的ではない。
第6次エネルギー基本計画では、デジタル化による省エネルギーを進めるとして、「シェアリングなど人・物・金の流れの最適化」「テレワークによる移動に伴うエネルギーの削減」「クラウド化による企業システムの省エネルギー」「エネルギーマネジメントシステムの高度化」などについて記述している。また、運輸部門については「物流分野におけるデジタル化の推進」「サプライチェーン全体での大規模な物流効率化、省力化を通じたエネルギー効率向上も進めていく」などとし、「エネルギー消費原単位の小さい輸送手段への転換を図る」「共同輸配送」「輸送網の集約」などの記述がある。こうした記述は第7次エネルギー基本計画では削除されていることの理由を明確にすべきである。
5.1.5℃目標
(1)エネルギー基本計画は、地球温暖化対策計画と相互に連動する関係にある。日本も批准しているパリ協定にある世界全体の気温上昇を1.5℃までに抑える目標を第7次エネルギー基本計画にも書き込み、同時にそれに整合する削減目標とエネルギー政策を掲げる必要がある。
近年、世界の平均気温は上昇し異常気象が頻発している。日本を含む先進国が削減目標をより強化することは急務である。そのためには、化石燃料からの脱却、とりわけ石炭火力のフェーズアウトが必要である。
現状のエネルギー基本計画案では、この観点が欠落している。1.5℃目標を明記し、より高い削減目標、化石燃料からの脱却を書き込むべきである。
IPCCは第6次統合評価報告書において、世界の気温上昇を1.5℃までに抑えるためには、世界全体で温室効果ガスを2030年までに43%、2035年までに60%(いずれも2019年比)以上削減する必要があるとしている。政府が掲げる削減目標では2050年炭素中立に向けて現状から直線的な削減を想定しているが、2040年までに急速な削減が必要なIPCCの1.5℃目標の道筋からは乖離した想定である。
6.原子力
(1)原子力を「他電力と遜色がないコスト水準」(p.34)などとしているが、発電コスト検証ワーキンググループによる原発のコスト試算は大幅な過小評価であると言わざるを得ない。
原発新設費用を、7,203億円( 建設費 5,496億円 + 追加安全対策費 1,707億円)としているが、近年建設されている原発の実際の費用は、フィンランドのオルキルオト原発3号機1.7兆円、米ボーグル原発一基当たり2.2兆円、仏フラマンビル原発2.1兆円、英ヒンクリーポイントC原発一基当たり4兆円以上(見込み)となっており大幅な過小評価である。諸外国との試算がこれほど異なる説明が必要である。追加安全対策費が設置許可変更申請している原発すべてとなっているが、実際の安全対策費は申請時のコストよりも大幅に増えることが多いため、過小評価となっている。また、廃炉費用に、デブリ取り出し以降の放射性廃棄物処分費用が含まれていない。
事故発生頻度が、4000炉年に1回から12000炉年に1回に変更となっており、安全性が向上したからとしているが、事業者自身がさらなる安全確保を目的として実施している「安全性向上評価」は、自主的主観的なものに過ぎず、コスト試算に使うことは非科学的である。(p.34ほか)
(2)原発を「優れた安定供給性」を有する(p.34ほか)としているが、誤りである。原発は固定的な大規模集中型電源であるがゆえの脆弱性、不安定さを有している。「一定出力である」ということは、調整力に欠けるということである。また、原発はトラブルが多く、1997~2010年までの事故故障等の報告件数は267件にものぼる。深刻な事故を回避するために、トラブルの内容によっては他の原発も停止して点検・評価する必要がでてくる。計画外に停止すればその影響は広範囲に及ぶ。(p.34ほか)
(3)原子力防災(p.35):現在、地域の「緊急時対応」が「地域原子力防災協議会」で策定され「原子力防災会議」で了承されるという枠組みであるが、「原子力防災会議」では実質的な審議は行われず、時間も5分程度の形式的なものである。避難計画も含む原子力防災計画を、設置変更許可申請の審査対象文書の一つとし、原子力規制委員会による審査の対象とすべきであり、原子炉等規制法に位置づけるべきである。(p.35)
(3)「自然災害との複合災害」(p.35):能登半島地震においては、多くの家屋が倒壊し、道路も通行不能となり、万が一原子力複合災害が発生した場合、屋内退避も避難もできない状況が起こりうるということを改めて示した。とりわけ即時避難が必要な5km圏(PAZ)においてもこうした状況になりうることは、住民が放射線による「確定的影響」を回避できない事態に陥りうることを示している。いったんすべての原発を停止し、能登半島地震等を踏まえた包括的な検証を行うべきである。(p.35, 36)
(4)「核燃料サイクルの推進」(p.36)核燃料サイクルはすでに破綻しており原子力政策の失敗典型事例である。六ケ所再処理工場は、27 回も工事完成が延期されており、いつ稼働するかもわからない上、事業費は15兆1,000億円に膨れ上がって今後も上昇を続けていくとみられる。稼働したとしても、すでに老朽化しているため、安全性に疑問があり、大量の放射性物質を環境中に放出するなどさまざまな問題を生み出す。取りだされるプルトニウムについては、プルサーマルで消費できる量はごくわずかであり、使用済みMOX燃料の処理もできない状況である。こうした状況を直視し、核燃料サイクルから即時撤退すべきである。(p.36-37)
(5)「中間貯蔵施設等に貯蔵された使用済燃料は六ヶ所再処理工場へ搬出するという方針」(p.36)は従来の資源エネルギー庁の説明と異なる。中間貯蔵施設は、当初は六ヶ所再処理工場で処理しきれない使用済み核燃料を貯蔵することを想定しており、「第二再処理工場」に運び出すとしていた。その後、「第二再処理工場」の計画はうやむやになり、資源エネルギー庁は「そのとき動いている再処理工場に運び出す」としていたが、今年になって市民への説明でh「六ヶ所再処理工場に搬出する可能性もある」としていた。稼働するかどうかわからない六ヶ所再処理工場を搬出先として挙げることに対する反発の声も多かった。今回、さらに「可能性もある」という文言が削除された。なし崩し的に説明を少しずつ変えるのは誠実性に欠ける。変更した理由を説明すべきである。(p.36)
(6)「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働への理解が進むよう…政府を挙げて対応を進める」(p.39):これは「再稼働ありき」の結論を地元の市民に押し付けるものであり、不適切である。現在、柏崎刈羽原発の再稼働は「地元同意」が焦点となっているが、政府が介入することにより、地元における冷静な議論をさまたげることになる。その他の原発についても「再稼働に向けて理解活動に取り組んでいく」とするが、同様の弊害が生じるため、やめるべきである。(p.37)
(7)「60年の運転期間のカウントから除外することを認める新たな制度」(p.39)は60年以上の稼働を許すものであり、撤廃すべきである。原子力規制委員会の高経年化に関する審査は、事業者の確認にもとづくものであるが、事業者が確認できる範囲は限定的であり、信頼性にかける。原発の配管、電気ケーブル、ポンプ、弁などの各部品や材料が、時間の経過とともに劣化するが、交換ができないものも多く、確認が難しい部分も多い。老朽化した原発を動かすべきではない。(p.39)
(8)「次世代革新炉の開発・設置」(p.40)は撤回すべきである。原発新設は巨額の費用がかかり、建設期間も長期化する傾向にある。原子力事業者のみでは負担することができずに、RABモデルのような新たな制度により、国民に負担を強いることになる。また、核のごみの処分に目途が立たない中、これ以上、放射性廃棄物を生み出すべきではない(p.40)。
(9)「世界では、原子力の利用が今後拡大する見込みであり」(p.41)としているが、世界の原子力発電は横ばいであり、世界の総発電量に占める原子力の割合は下降傾向にあるという現実からして前提が不適切である。(p.41)
(10)「東京電力福島第一原子力発電所事故の経験から得られた教訓を国際社会と共有する」(p.41)としているが、本来共有すべきは、原発の過酷事故の悲惨さや14年もたとうとしているのにいまだに故郷に帰れない人たちの思い、放射線被曝の現実、目途のたたない廃炉の現実であることを明記すべきである。(p.41)
7.火力発電の延命、水素・アンモニアの脱炭素効果
火力発電の「脱炭素化」による延命ではなく、火力発電からの早期の脱却こそめざすべきである。
LNG火力には水素を、石炭火力にはアンモニアを混焼することで「化石燃料の脱炭素化」をしていくとするが、これには莫大なコストがかかる。また当面は化石燃料由来・海外製造の水素・アンモニアを輸入して利用する計画であり、温室効果ガス排出量は実質的に増える。一部再エネ由来の水素・アンモニアが実現するとしても、発電以外の排出不可避分野での使用に限定すべきである。
CCSについても、国内では適地が限られ、2050年までのロードマップで示される量(年間1.2~2.4億トン、日本の温室効果ガス排出量の1~2割、圧入井240~480本もしくはそれ以上)の実現はまったく見通せない。マレーシア等にCO2を輸出しての貯留も検討されており、国内外から批判の声があがっている。
水素・アンモニアやCCSに関しては、民間では支えきれないコストを政府が支援することがGX基本方針等ですでに決められ、具体的な政策策定に進んでしまっている。温室効果ガス排出削減につながらず、化石燃料の利用をむしろ延命する新技術に頼りながら火力発電を使い続けることはやめ、その資金を省エネ・再エネに振り向けるべきである。(p.41-43)
8.鉱物資源
(1)真の「公正な」エネルギー移行のためには、国内外また陸海問わず、鉱物資源の際限ない採掘から脱却しなければならない。第7次エネルギー基本計画案では、鉱物資源等の海外権益獲得や安定供給の重要性が強調されているが、鉱物資源開発の現場で従来起きてきた自然・生態系の破壊、貴重な生物多様性の喪失、土地の収奪、人々の暮らしの破壊、超法規的殺害を含む深刻な人権侵害などが、気候変動対策の名の下に繰り返されることがあってはならず、鉱物資源の可能な限りの需要削減が大前提である。このため、エネルギー・電力の需要抑制を最優先で進め、公共交通機関の利用促進、カーシェアリングなどによる自動車の削減にも積極的に取り組むべきである。(p.31, p62-64, p70 ほか)
(2)鉱物資源開発は広大な面積の開発を伴うため、プロジェクトレベルの環境社会影響の緩和には限界がある。鉱物資源の開発を前提とするのではなく、保護価値の高い生態系に影響が及ぶ開発を行わない、先住民族や現地住民が鉱山開発を拒否する権利を保護・尊重する、企業による責任ある鉱物調達を徹底するなどの取り組みを実践していくことが重要である。
(3)第7次エネルギー基本計画案では、デジタルトランスフォーメーションやグリーントランスフォーメーションの進展に伴う電力需要増加を前提に、銅やリチウム、ニッケルなど重要鉱物の安定供給に関するリスクを日本の産業側の立場で強調している(pp.62-63)。しかし、採掘現場における自然・生態系の破壊(水質汚染、森林伐採など)や人権侵害(土地収奪、生計手段の喪失、健康被害、採掘に反対・懸念の声をあげるコミュニティへの弾圧など)など深刻な問題について、生産現場における住民や先住民族からの視点が欠如している。(p.31, p64, p70 ほか)
9.策定プロセスへの批判と今後への期待
第7次エネルギー基本計画案には随所で「双方向のコミュニケーション」の重要性が強調されているが、実際には同案策定過程において、一般市民の声を聴取する機会は「意見箱」とパブリックコメントに限られている。全国約10ヶ所で「説明会」が開催されることとなったが、あくまで「説明」であり、その意見を反映するものではない。閣議決定の前に全国で公聴会を開催し、パブリックコメントとともに市民の声を聴取、検討、反映すべきである。世論調査、討論型世論調査など複数の手段を組み合わせるべきである。
エネルギー基本計画について議論する審議会「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」では気候変動、再エネ推進事業、自治体や地域電力に取り組む生協、SDGs、原発事故などに関わる専門家や当事者、環境NGO、そして若い世代も含めて議論を行うべきである。
冒頭でも述べた通り、国は再生エネルギーについて、世界の動向を国民に正確に伝えることを怠っている。再生可能エネルギーの負の面を強調し、原子力や化石燃料技術の維持・推進が強化に尽力することは国民のエネルギー政策についての期待に全く反しているという点を強調したい。
高コストの発電に電力供給の3~4割を依存する体質の根本的改革こそ、電気料金の高騰を防ぎ、企業の国際競争力を高め、ひいては国力の維持発展に資するものである。(p82)
以上
パブコメを出すにあたり留意してほしいこと
日本政府の目標値はいずれも低く、WWFほか様々な団体・研究機関が2035年や2040年の温室効果ガス排出削減目標について提言しています。
<参考>【WWF声明】GHG排出量2013年比66%削減という最低限の水準すら下回る2035年NDC案に抗議する
WWFより
エネルギー基本計画の案に求められる改善点
◇ポイント①:2040年電源構成での再生可能エネルギーの割合を大幅に引き上げるべき
政府案では、再生可能エネルギーを最大限導入していくことが示されている一方で、特定の種別の電源に過度に依存しないようにすることが念押しされています。その上で、関連資料では、2040年時点での再生可能エネルギーの割合を4~5割にすることが示されています。
しかし、1.5度に整合した電源構成とするには、再生可能エネルギーの割合をもっと引き上げる必要があります。上記の4~5割という水準は、政府案を議論した審議会でのヒアリングで、2040年の再生可能エネルギーの割合を40~60%とする分析がほとんどだったことを背景としていますが、これらのシナリオはごく限られた研究機関の結果にすぎません。
他方、その他の研究機関からは、2040年代に70%~ほぼ100%にできることが示されています。WWFジャパンも分析を行なっており、2040年には電力の90%を再生可能エネルギーで賄えると試算しています。これら高い水準は電力の安定供給とも両立でき、決して不可能ではありません。
加えて、日本の企業をはじめとした幅広い主体からも、再生可能エネルギーの大幅な拡大が求められています。気候変動対策に前向きな企業や自治体などからなる「気候変動イニシアティブ(JCI)」は、再生可能エネルギー導入の最大化などを求めるメッセージを発表し、そこにはプライム上場企業77社を含む236団体が賛同しました。
また、日本経済新聞が2024年12月に実施した「社長100人アンケート」でも、石破政権に期待する政策では「再生可能エネルギー拡大」に最も多くの票が投じられました。(日本経済新聞2025年1月9日付朝刊)
さらにこうした声は日本で事業を行う海外の需要家たちからも寄せられています。再生可能エネルギーの電力使用100%を目指す企業の国際イニシアティブ「RE100」、エネルギー需要家などからなる国際団体「Clean Energy Buyers Association(CEBA)」、半導体製造における産業発展を目指す国際団体「SEMI」も、日本政府に対し再生可能エネルギー導入を加速する高い目標や施策を求める提言を発表しています。
このように、再生可能エネルギーを大幅に導入できるかは、日本経済の国際競争力に直結するという認識が広く持たれていることが窺われます。
◇ポイント②:化石燃料からの転換に明確な道筋をつけるべき
政府案は、非効率な石炭火力発電の使用を段階的に止めていくとしつつ、ガス火力の活用のためにLNGの安定供給確保や、火力発電の「脱炭素化」に向けた研究開発・実装を目指しています。また、関連資料での電源構成でも、火力を3~4割としています。
こうした方向性は、2023年のCOP28(国連気候変動枠組条約第28回締約国会議)で合意した、「今後10年間で化石燃料からの転換に向けた取り組みを加速」という内容に整合しません。
特に日本において石炭火力は非効率なものに限らず、遅くとも2030年までには段階的にすべて廃止しなければなりません。石炭は最も効率的な発電方法でも、ガス火力の2倍程度の温室効果ガスを排出するためです。
また、国際的にも石炭火力の廃止に向けた機運は強まっています。2024年のG7首脳宣言では、G7各国で2030年代前半までに段階的に廃止することが合意されており、日本もこれを遵守する必要があります。
WWFジャパンの分析では、省エネの追求や、国内での再生可能エネルギー導入拡大、既存ガス火力の稼働率の向上で、電力供給に問題を生じさせずに石炭火力を廃止できることが判明しています。今こそ石炭火力の廃止に向けた具体的なスケジュールが必要です。