本の紹介 日本の電力システムを考える際にぜひ知っておくべきことが満載
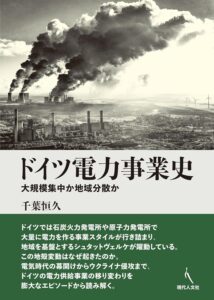 千葉恒久さん著 『ドイツ電力事業史~大規模集中か地域分散か』 (2024年 現代人文社 490頁)
千葉恒久さん著 『ドイツ電力事業史~大規模集中か地域分散か』 (2024年 現代人文社 490頁)
本書はドイツの電力事業の歴史を追った本ですが、異色の事業史と言えます。著者のねらいは、「エネルギー転換がなぜ進んでいくのか」という問いに答えることにあるからです。
著者は、事業を拡大して市場を支配しようとする電力会社とそれに対峙しようとする自治体(シュタットヴェルケ)との間を何度も行き来しながら、電力事業が誕生したおよそ150年前から現在までの間に、事業の現場で起きた様々な出来事を追っています。
本書を読むと、両者の間で電力事業の針路をめぐる攻防がずっと続いて来たこと、原発などの大型の発電所が作られるようになる過程では戦争が決定的な影響を与えたことがわかります。著者は、電気というものが広まる過程では私たちの家庭での生活、とりわけ女性の自立も深くかかわっていたこともわかっていた、といいます。こうして、話は電気冷蔵庫と原発とのつながりにまで及んで行きます。
著者は、大型化と広域化に向かった歴史は石油ショックを契機に反転し、その後は大手電力会社の事業基盤が草の根の市民の運動や電力事業の自由化によって掘り崩されて行く過程が進行している、と指摘しています。本書の後半ではその過程をつぶさに追っており、そこが本書のクライマックスと言えます。一見すると強大に見える大手電力会社はすでに砂上の楼閣なのではないのか。本書は読者にそう問いかけます。
本書を読むと、ドイツの歴史が日本にもあてはまる部分が非常に多いことにも気づかされます。私たちは、いま目の前にある電力事業の姿にとらわれがちですが、本当に必要なのは自由な発想で電気(エネルギー)というものについて考え直すことなのではないか。そう思わせる一冊です。500頁近くある本ですが、一読をお勧めします。
はじめに
本書で使用する表記など
略号
関連年表
ドイツ地図
第1部 電力供給事業はいかに形成されたのか
1 シュタットヴェルケの誕生(1880年代~1910年代)
2 広域供給事業の台頭(1900年代~1910年代)
3 電力供給事業に触手を伸ばす国(1910年代)
4 神話の誕生(1910年代)
5 電力供給事業の戦争と平和(1920年代)
6 追い込まれる地域供給事業(1920年代)
7 独裁下の綱引き(1930年代~1945年)
8 再び回り始めた歯車(1945年~1960年代)
9 飼いならされた産業施設(1900年代~1960年代)
10 独占に切り込め(1960年代~1970年代)
11 電気はいかにして家庭に入り込んだのか
第2部 大規模供給事業を襲った変革の波
1 トレンドが消えた(1970年代~1980年代)
2 地域発の新しい風(1980年代)
3 自由化の真の狙い(1990年代~2000年代)
4 視界なきピーク(2000年代)
5 巨人たちの転落(2010年代)
6 シュタットヴェルケのルネッサンス(2000年代~2010年代)
7 ウクライナ侵攻(2020年代)
第3部 大規模集中か地域分散か
1 大規模供給事業の5つの弱点——大手電力会社はなぜ消えていくのか
2 シュタットヴェルケの原点
3 地域電力の存在意義
4 電力の地消を阻む壁
参考文献
あとがき
*千葉恒久さんは長年ドイツの電力事情を研究されていらっしゃる弁護士さんです。本書はその集大成ともいうべきものです。日本の制度との違いや今後の政策の指針も窺い知ることができる事典のような本です。
コンシューマネット・ジャパンの協力者です。本書はstoresでも販売しています。
https://consumernetjp.stores.jp/items/67b67a2ea8296c0296dcaa65
図書館や研究室にも常備してください。多部数については割引があります。
合わせて、千葉さんへの講演依頼をご希望の方は
info@consumernet.jp
にお問合わせください。講演の依頼も受け付けています。


